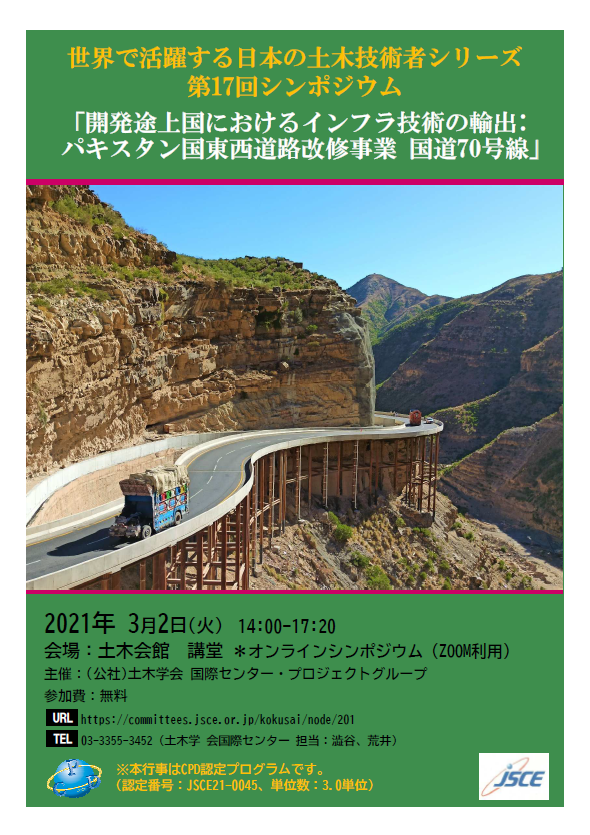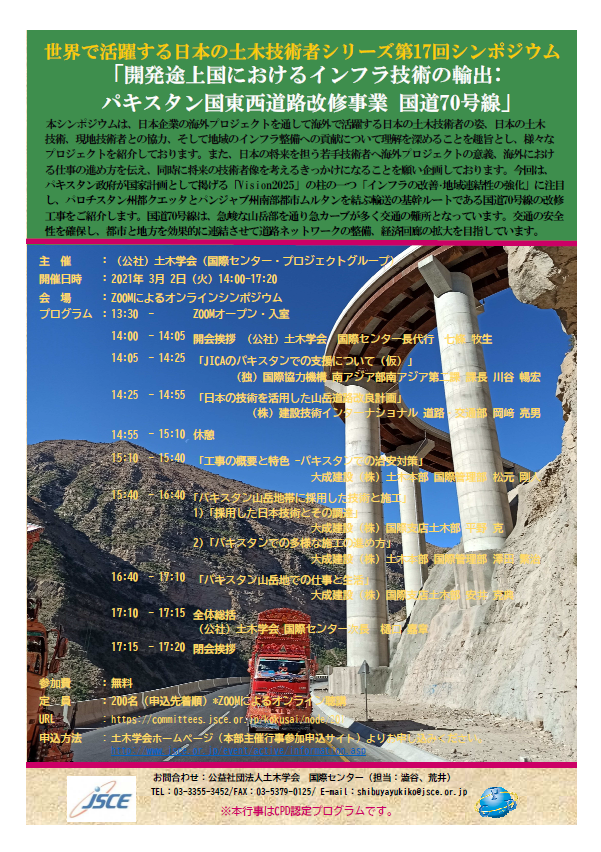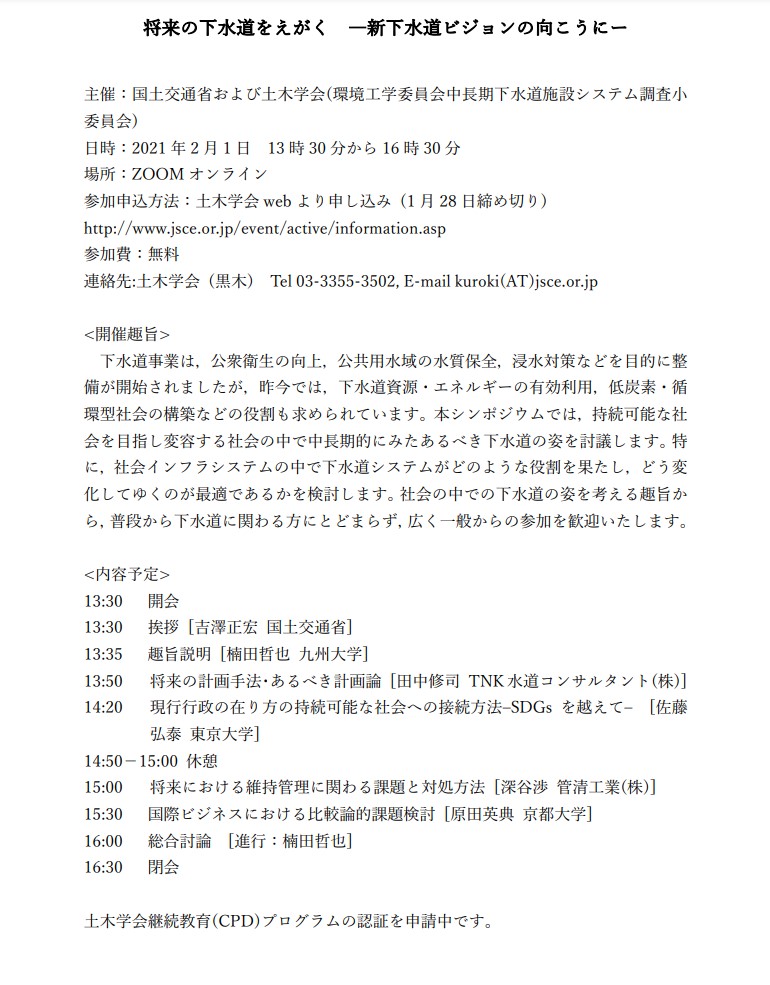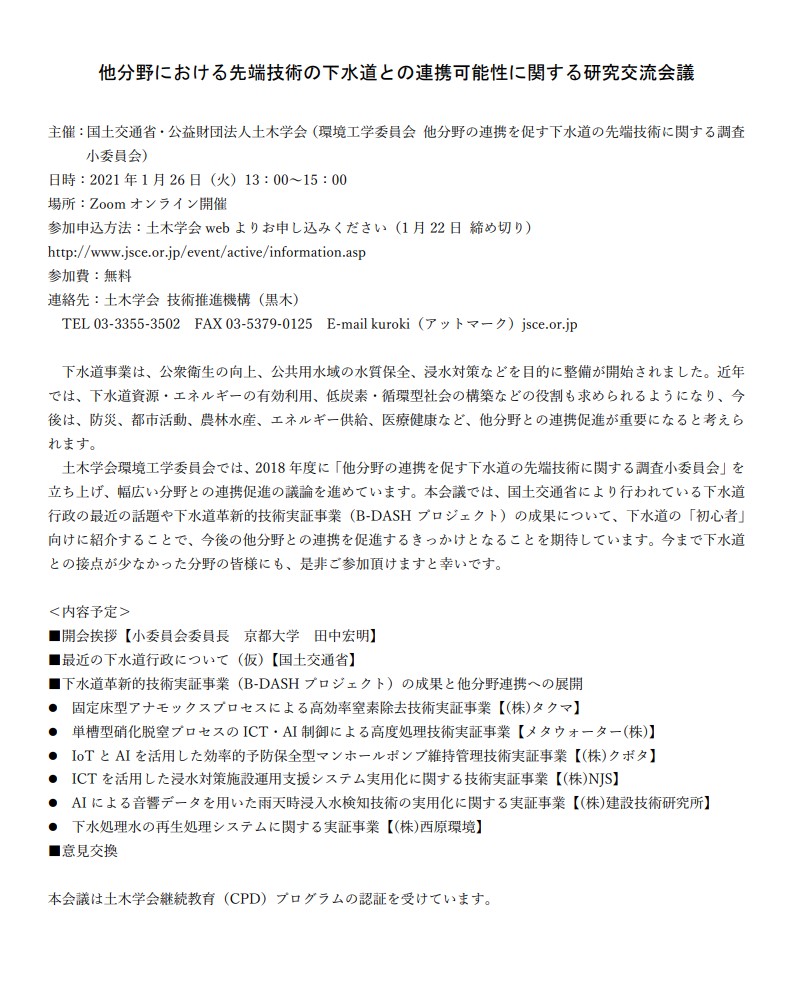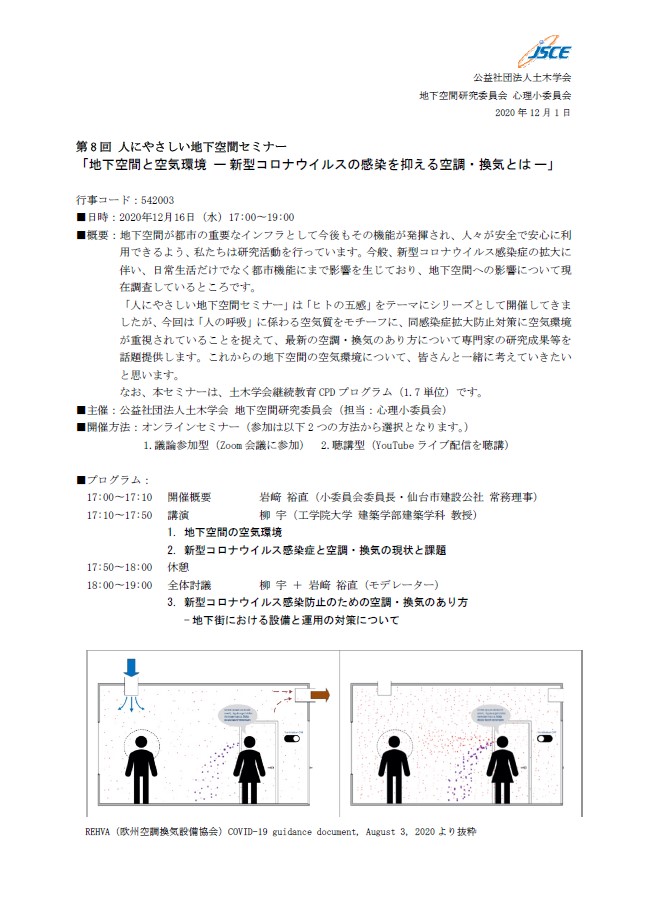公益社団法人土木学会(会長 家田 仁)は、1/12(火) に『第3回地方インフラを対象としたメンテナンス講座』をオンライン開催(YouTube)致します。
当会は、2020年度よりインフラメンテナンス総合委員会(注1)を立ち上げし、インフラメンテナンスと減災防災への新たな戦略的取り組みとして、基礎自治体を対象とした全4回シリーズのメンテナンス講座をオンラインにて開講しております。
第1回目(2020/11/16)の『導入編』、第2回目(2020/12/14)の『現状編』に続き、第3回目は、新技術適用推進小委員会(注2)と連携し、『新技術導入編』を開催いたします。
基調講演にて、地方のインフラメンテンナスにおける新技術の導入をご説明いただいた後、地方自治体の事例紹介を行い、最後に、ディスカッションとして、『地方インフラメンテに関する困りごと相談コーナー』を開催予定です。ぜひこの機会に、本オンライン講座にご参加いただき、理解を深めていただければ幸いです。
注1):これまで個別に活動していたメンテナンス関連委員会が、2020年度より統合。
注2):土木学会 インフラメンテナンス総合委員会 新技術適用推進小委員会https://committees.jsce.or.jp/opcet_sip/

記
第3回 地方インフラを対象としたメンテナンス講座
【詳細】
1.日時:2021年1月12日 (火) 13:00~15:20
2.会場:オンライン(YouTube)
≪注意事項≫ 動画のスクリーンショット・録音・録画・二次利用等は禁止いたします。
3.視聴URL:https://youtu.be/25sG8lCj26M(2週間のアーカイブ配信予定)
4.参加費:無料
5.申込み:オンライン視聴の事前申込み不要
※ただし、CPD受講証明を必要とする方のみ、必ず事前申し込みを行ってください。
6.主催:土木学会 インフラメンテナンス総合委員会
7.詳細URL:https://inframaintenance.jsce.or.jp/maintenancekoza/maintenance-course-2020-03/
8.プログラム:
13:00 開会挨拶:家田仁 氏(土木学会会長)
13:10 基調講演-1:
『地方インフラメンテのすすめ-新技術を活用してみんなで壁を乗り越えよう-』
野田徹 氏(清水建設/新技術適用推進小委員会委員長)
13:30 基調講演-2:
『地方インフラのメンテナンスに新技術を導入するためには-課題と解決策を考える-』
黒田保 氏(鳥取大学/地域実装促進部会長)
(休憩5分)
14:05 地域の実例紹介:
『ドローンを活用した橋梁点検』
古明地悠氏(千葉県君津市役所)
『データベースを活用した橋梁メンテナンス』
北澤真氏(秋田県大仙市役所)
14:35 ディスカッション:『地方インフラメンテナンスに関する困りごと相談コーナー』
コーディネータ 岩城一郎 氏(日本大学/アクティビティ部会長)
パネリスト:上記登壇者、六郷恵哲氏(岐阜大学)、若原敏裕氏(大崎総合研究所)
15:15 閉会挨拶:塚田幸広氏(土木学会専務理事)
【お問合せ先】
公益社団法人土木学会 インフラメンテナンス総合委員会
事務局担当:小川 TEL:03-3355-3559 E-mail: inframaintenance@ml-jsce.jp