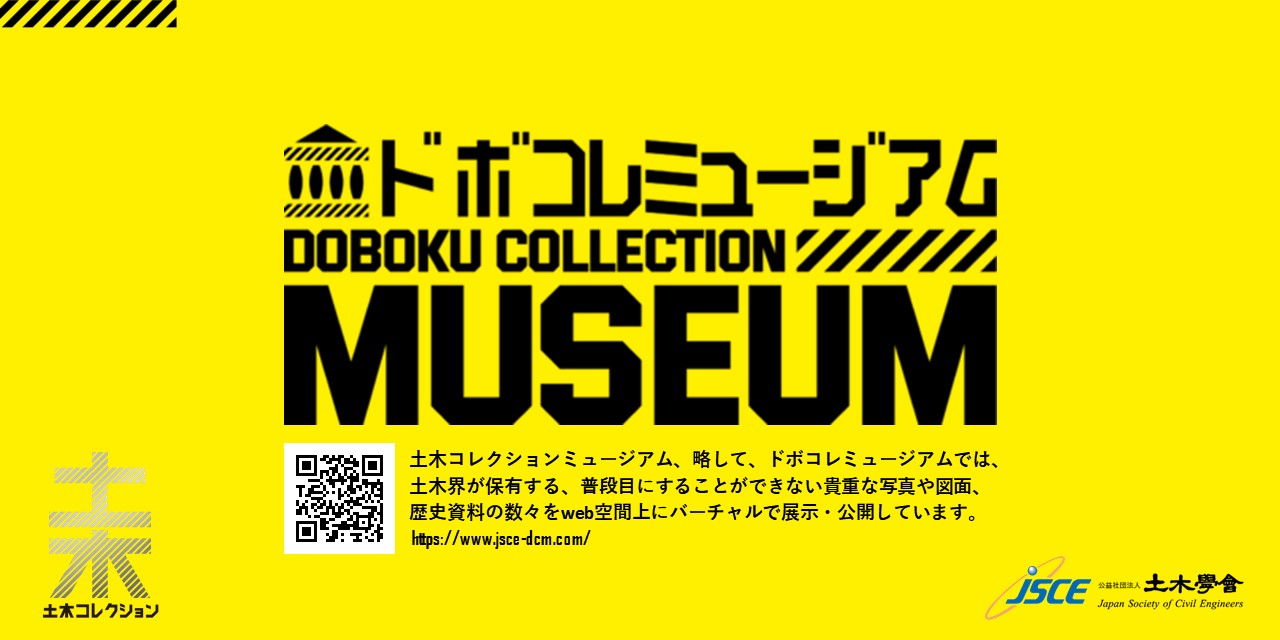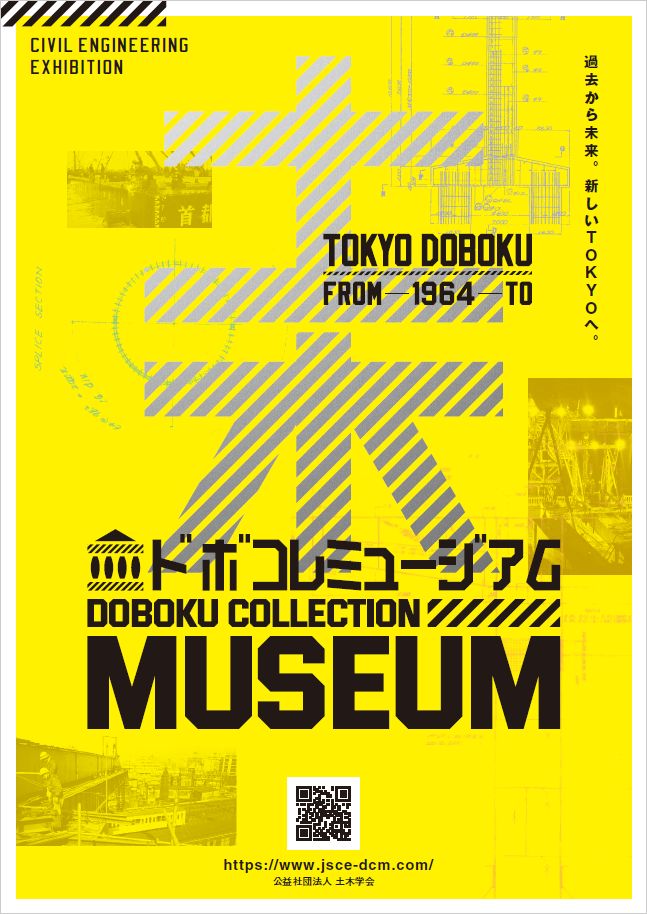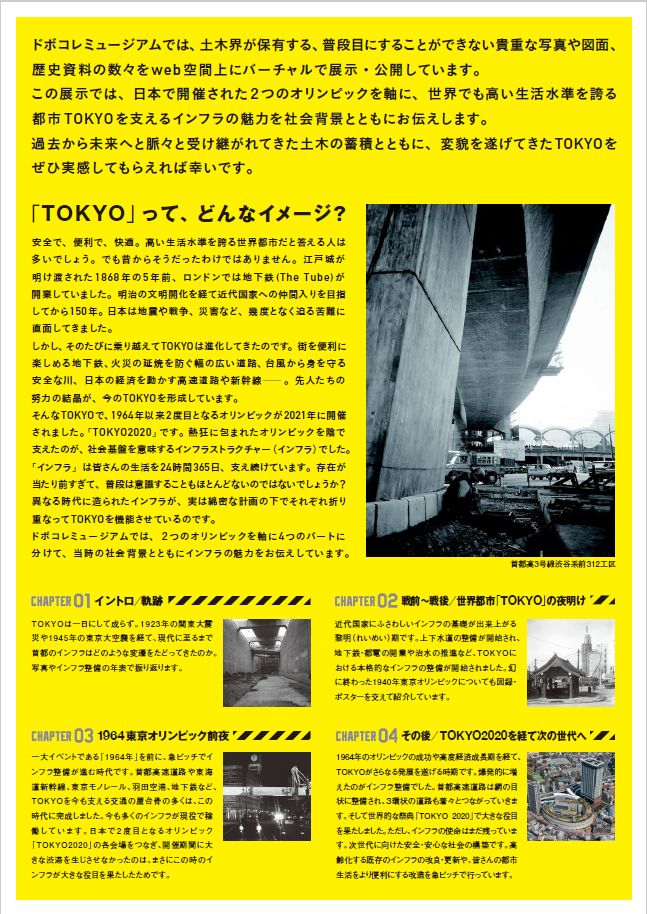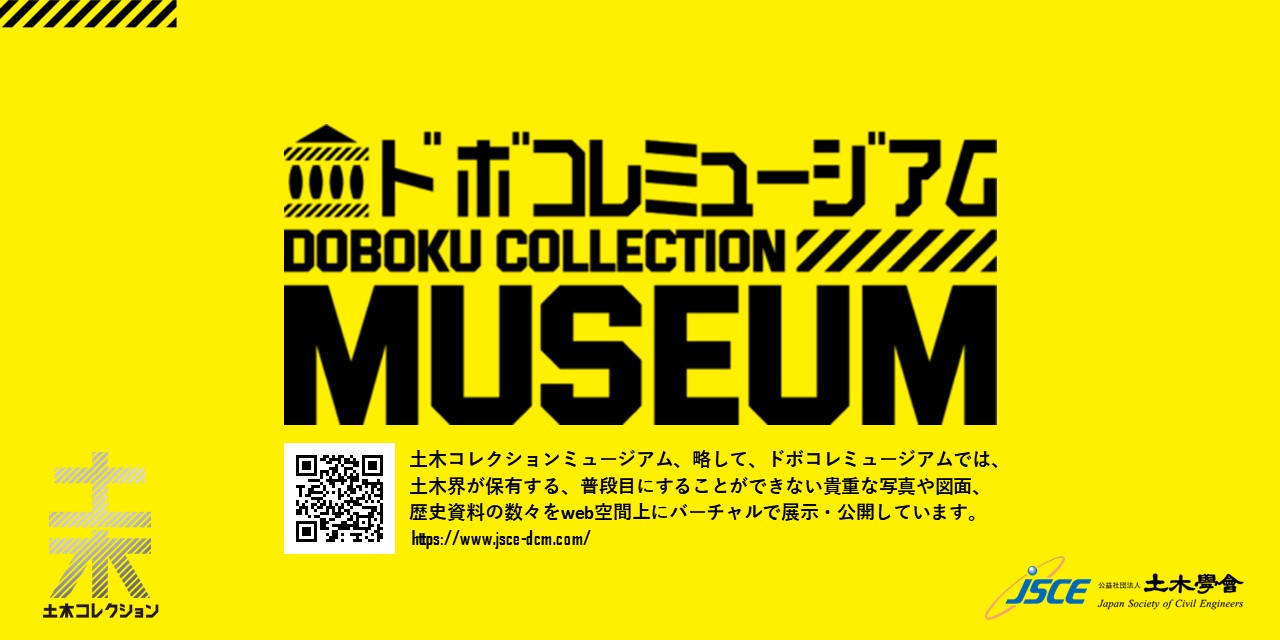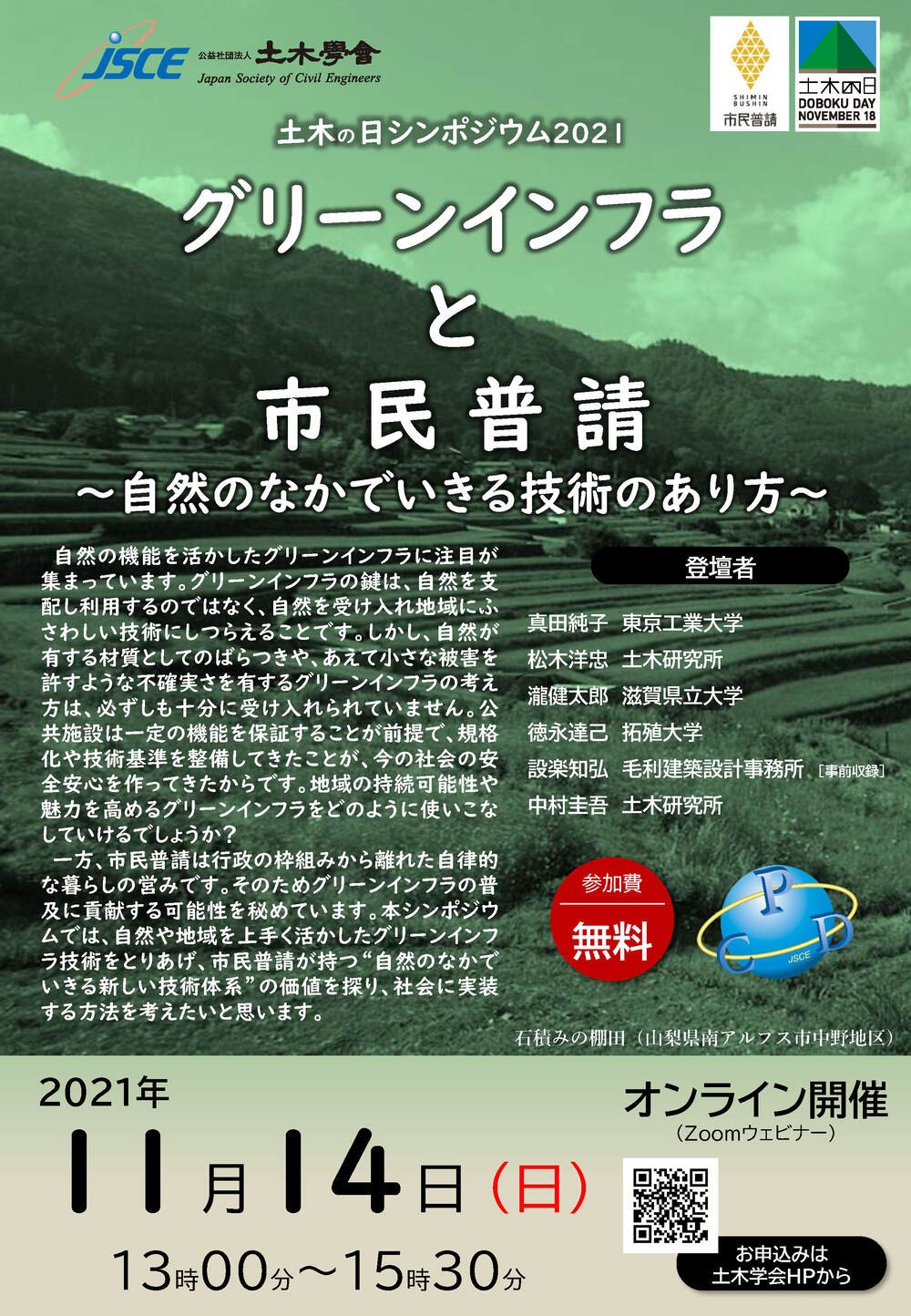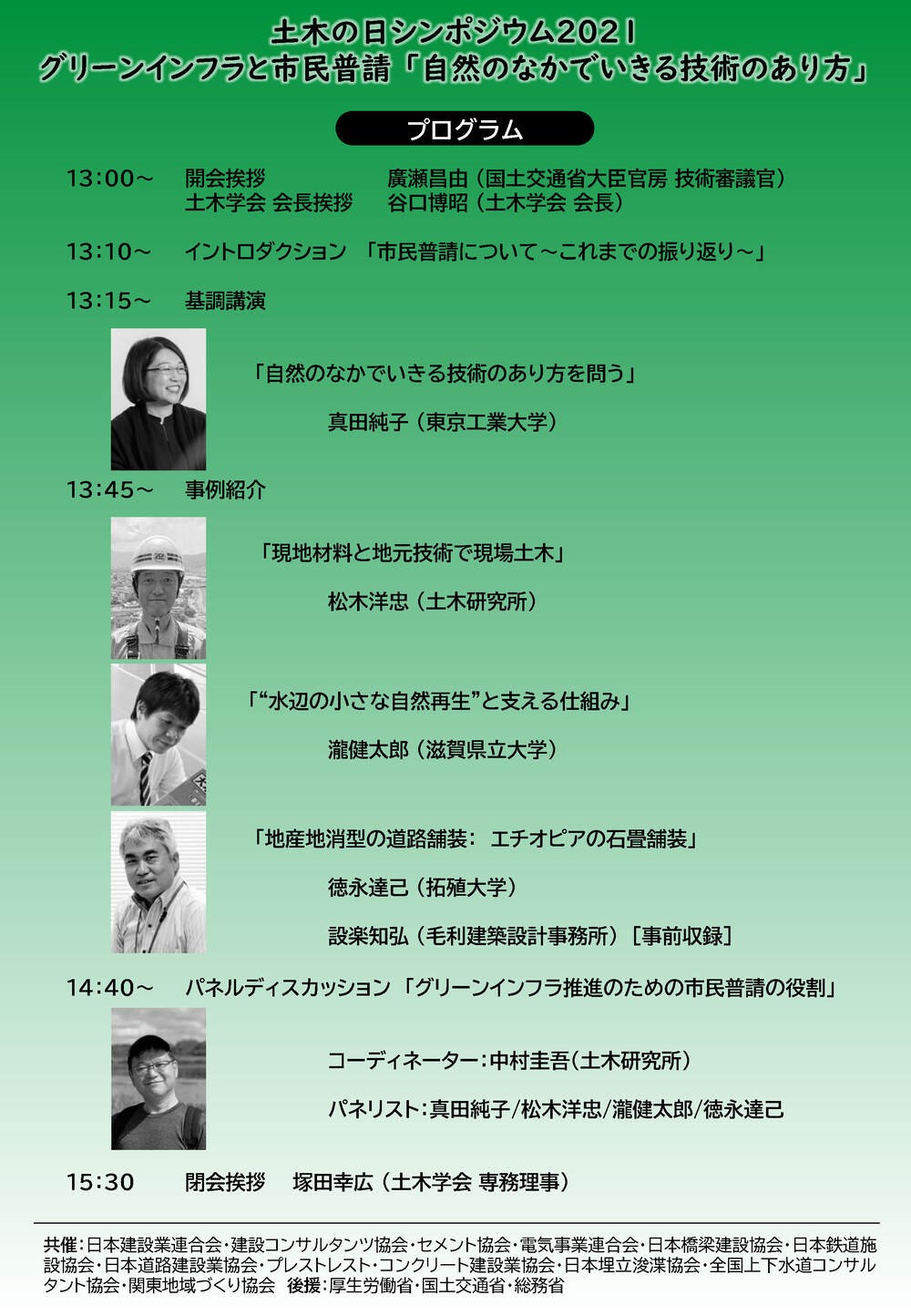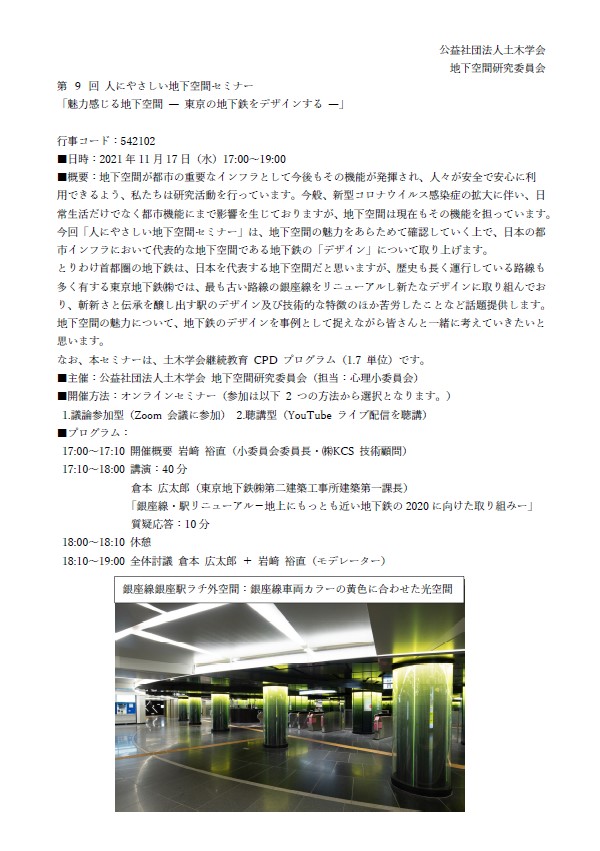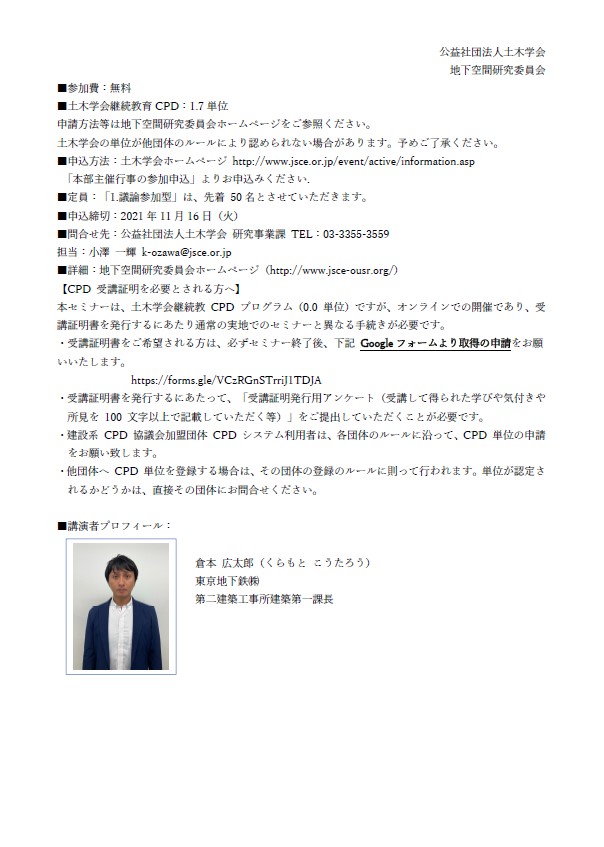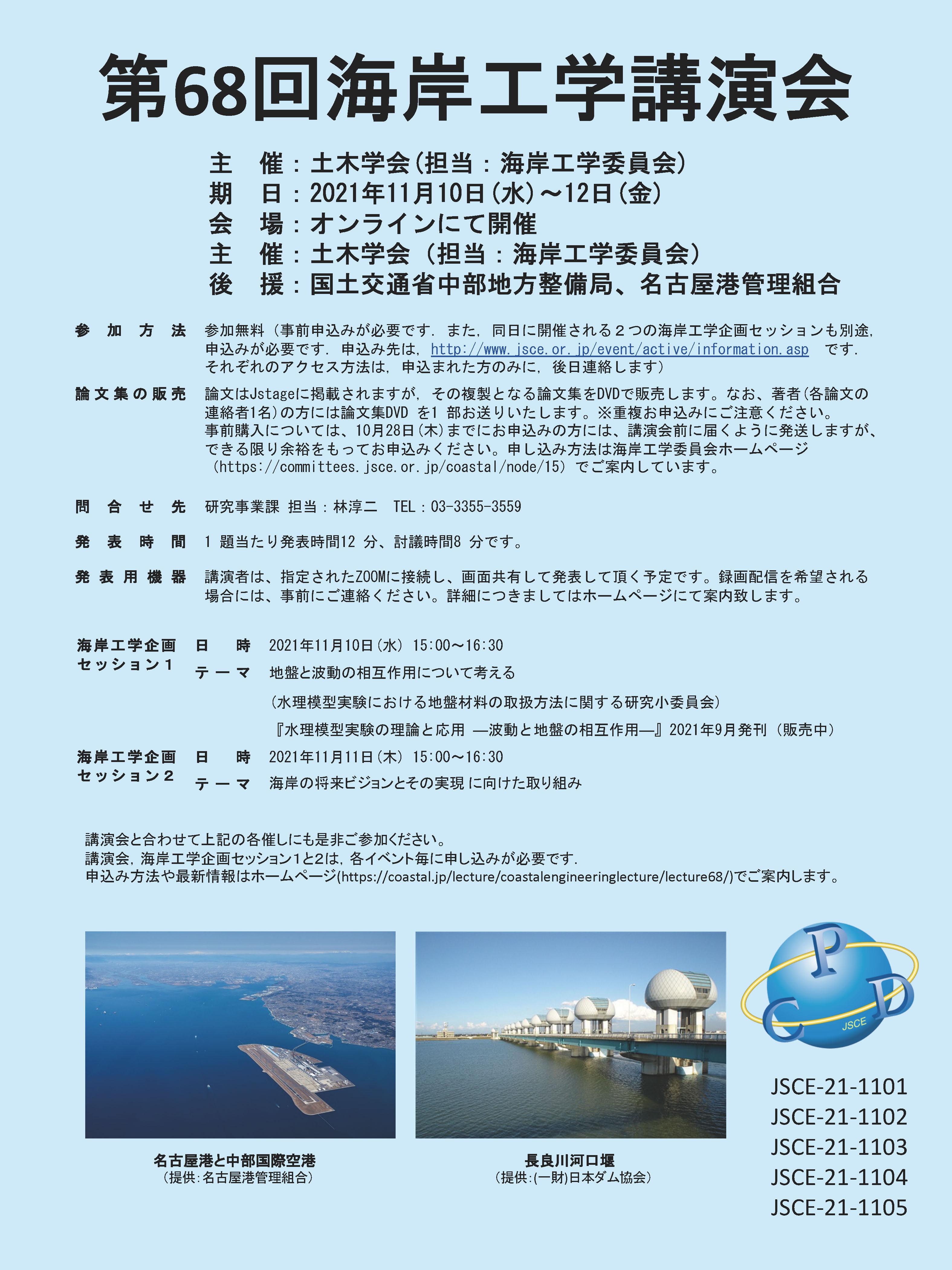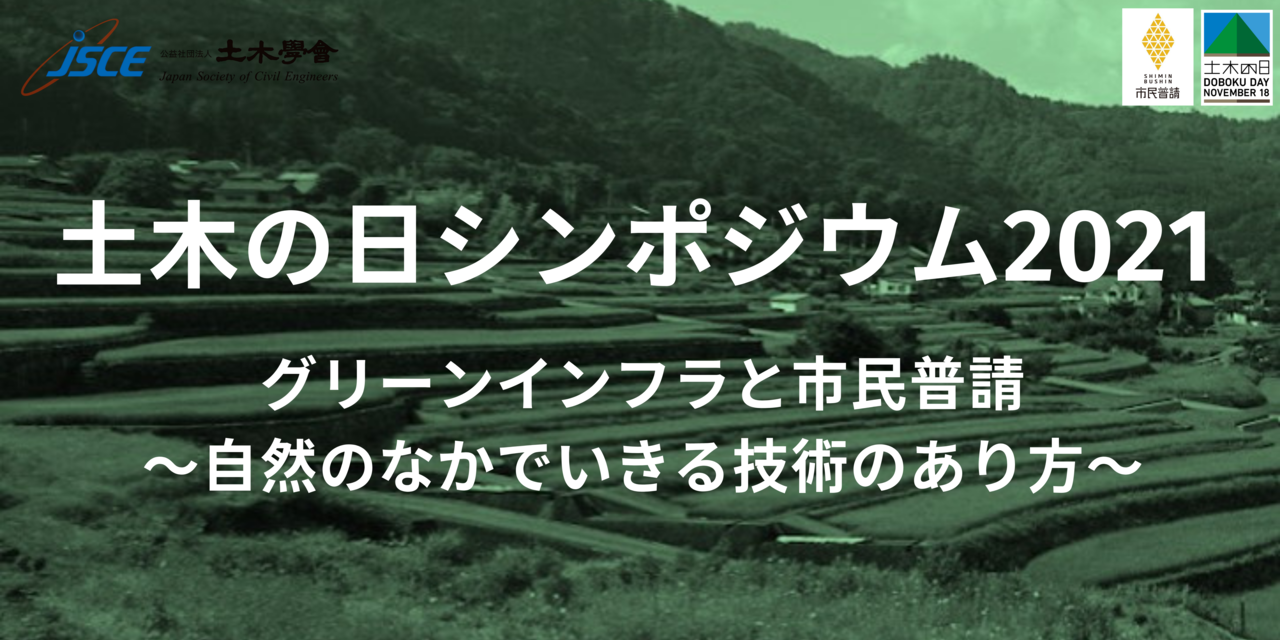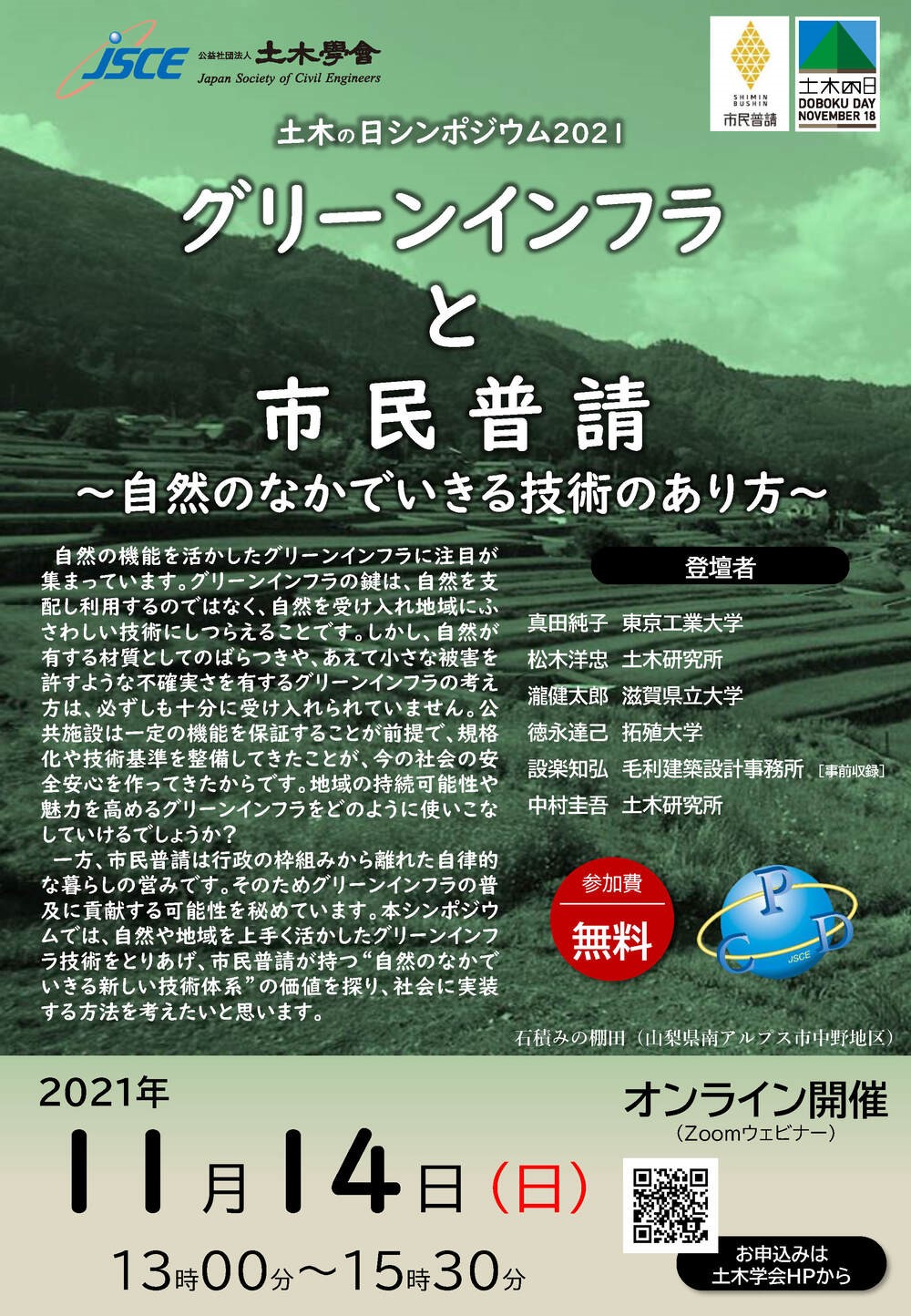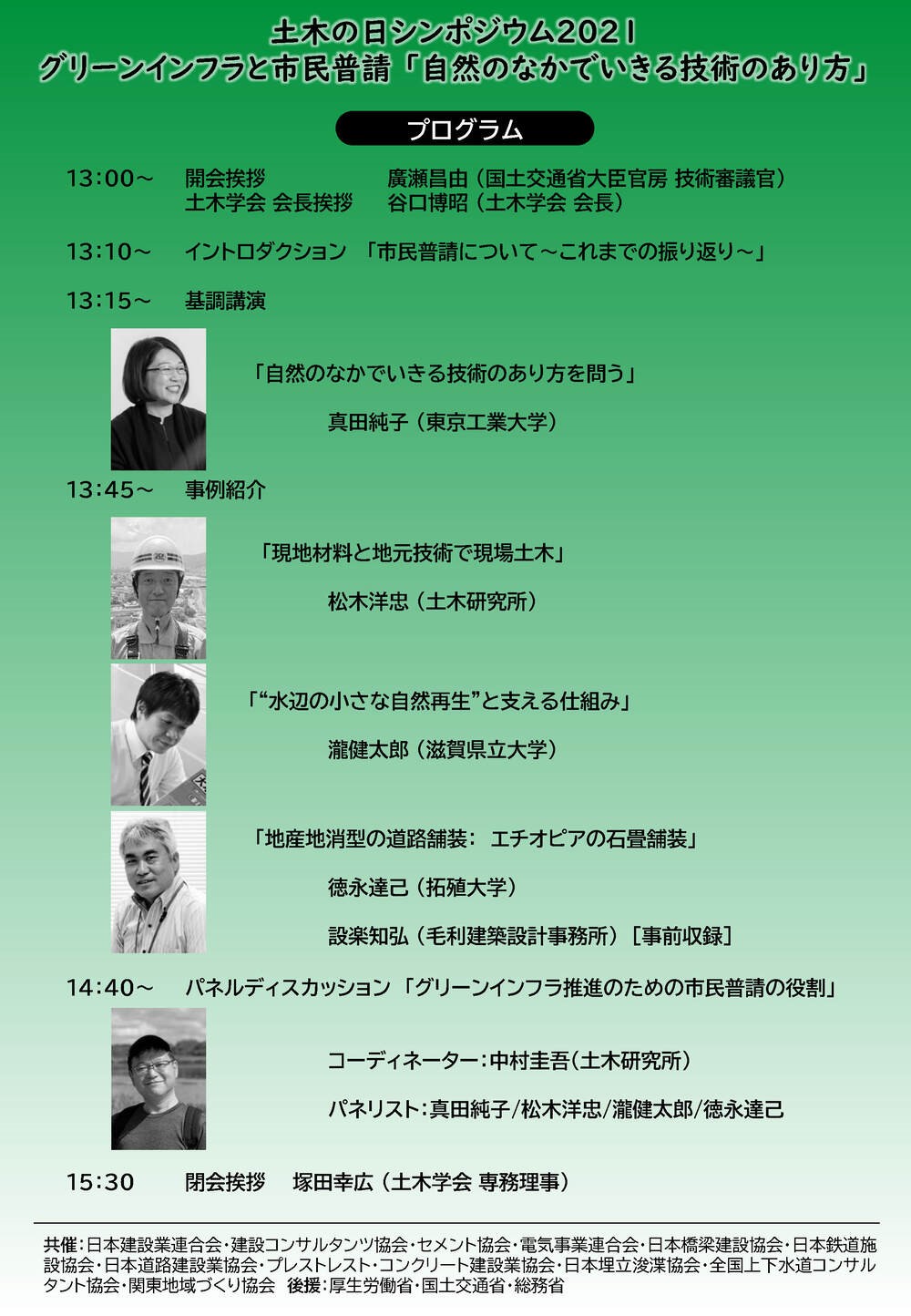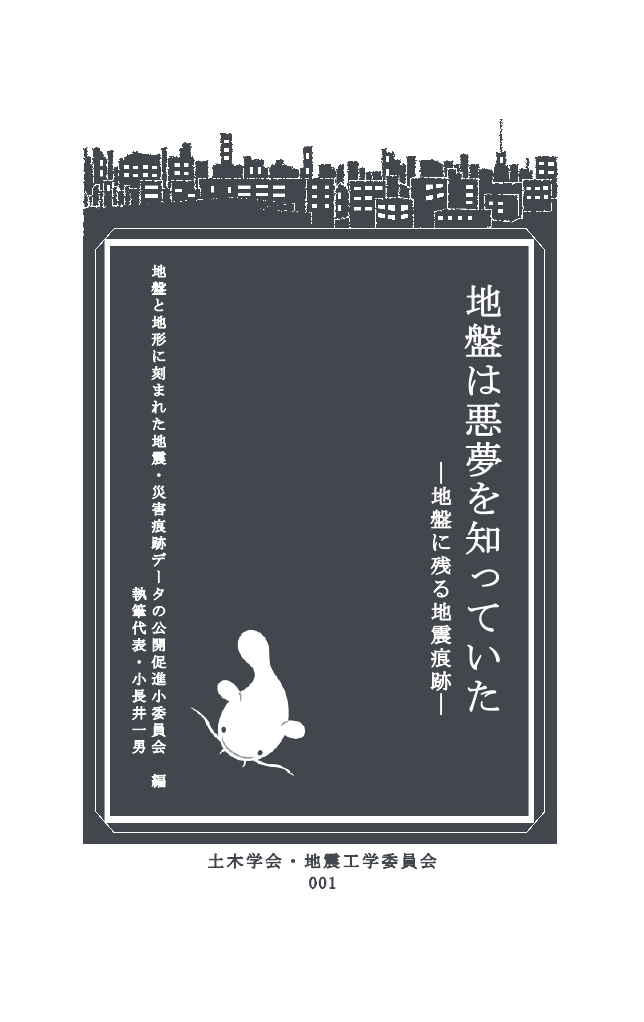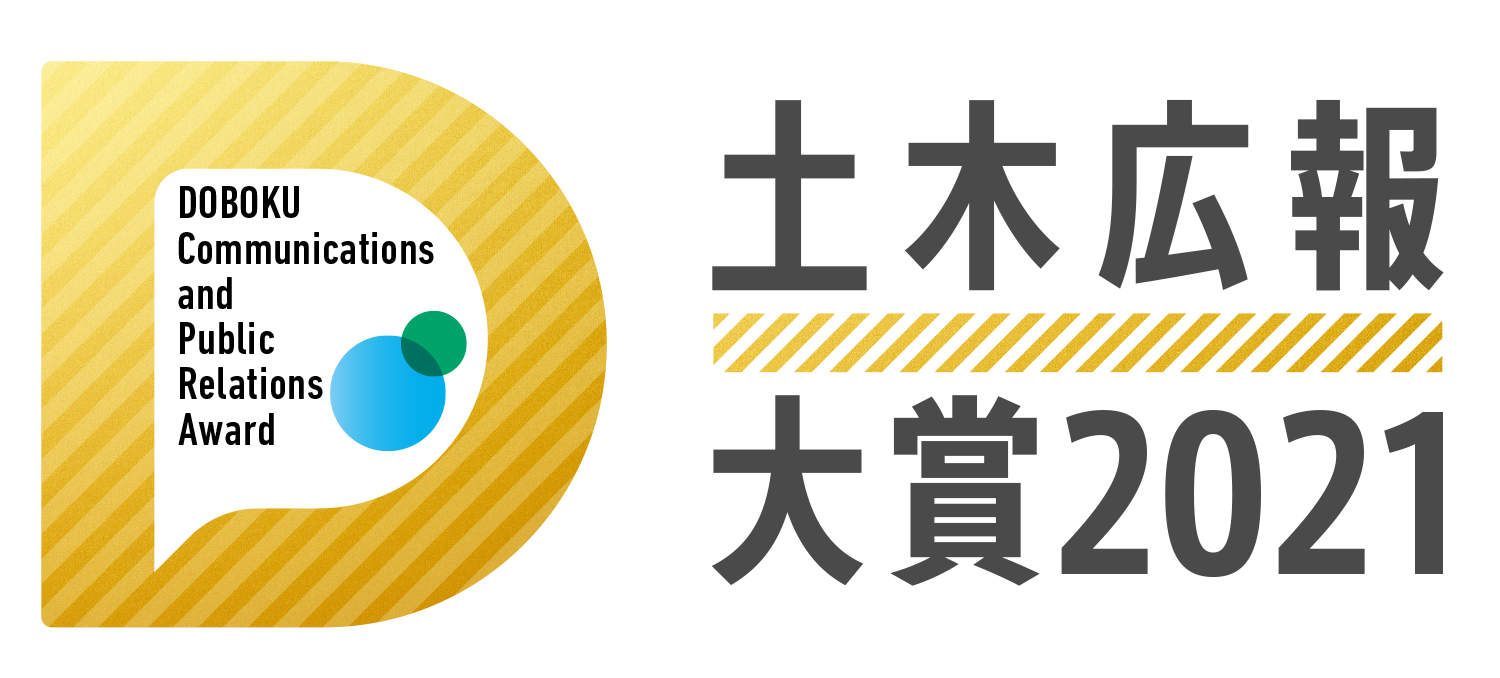グランプリは『「ちょっと近いが一番楽しい」場所を残す未来』(三浦えり様 作)
公益社団法人土木学会(会長 谷口 博昭、以下土木学会)は、メディアプラットフォーム「note」においてnote株式会社(本社:東京都港区、代表取締役CEO:加藤貞顕)と共同で、2021年9月8日から10月3日までの約一か月間にわたり募集していた投稿コンテスト「#暮らしたい未来のまち」の受賞作品を決定しました。
今回のコンテストには、期間中に1224件もの作品の応募があり、論文や学会誌、報告書など土木学会の活動の中で多く接する文章とは大きく異なる表現・内容で、多様な視点、多様な価値観から、それぞれが考える「暮らしたい未来」「暮らしたいまち」の姿を描いた、魅力ある作品の数々が集まりました。
厳正なる審査の結果、各賞が以下のとおり決定いたしました。
グランプリ / 審査員特別賞 / JSCE賞 / 入賞
グランプリ
「ちょっと近いが一番楽しい」場所を残す未来(三浦えり 様)
自身が住む「東京都港区」を描く連載の執筆をきっかけに、きらびやかなまちのイメージとは違った、地域の歴史や地理に出会った三浦えりさん。そこに住み続けるひとや昔から残る場所がつくる、歴史あるまちの個性を未来に残すために、自分ができることをつづった作品がグランプリに選ばれました。審査員からは、「今いる場所をとらえなおすという、本質的に大切なことを示している(大西さん)」「日本全国どのまちにも歴史があり、発見がある。自分の住むまちを愛せる人が増えるような、完成度の高いエッセイ(伊佐さん)」「暮らしたいまちの未来に向けて、自分にもできそうだと思える提案がよかった(青鹿さん)」「港区という大都市が題材だが、住む場所に関わらずすべてのひとに通じる、住んでいる場所を大切にしたいというメッセージに共感した(土木学会note担当)」と高い評価を受け、グランプリの受賞となりました。
審査員特別賞
今回、審査員を務めていただいた3名の審査員、伊佐知美さん・青鹿ユウさん・大西正紀さんに選んでいただいた審査員特別賞は以下の3作品です。
表情(かお)のある街に暮らしたい。(£ (ポンド) 様)
表情(かお)が見えるまちは、「暮らしたい未来のまち」の答えのひとつだと思わされました。表情とは、そのまちがもつ唯一無二の個性です。それは、そのまちを選び暮らし続けたい理由や、まちの未来を考えるきっかけになるのではないでしょうか。
また、住んでいる人にとって「当たり前」で、時につまらなく映る風景も、よそ者にとっては「面白すぎる場所」に映ることがある。そんな「個性」が自分が 暮らすまちにもきっと隠れているという、誰もが気づいてほしい視点が描かれていました。ぜひ多くの人に読んで、考えてみてもらいたい作品です。(伊佐知美さん)
人と自動車のための未来都市(太田英司 様)
私は個人的に、誰かの好きや推しが伝わる作品が好きなもので、他の交通機関や車が苦手な人を度外視しで車や道路推しなこの作品を面白いと感じました。
現実問題、可能かどうか沢山の課題があるとは思いますが、強い「好き」はそんな困難もよりよい形で変えていくのかも…!という気持ちになりました。
(青鹿ユウさん)
韓国生活20年。神戸・東京・ホノルル…そしてソウルへ。(nora_korea 様)
「まち」の素敵さとは、無限に多様なのだと改めて気づかされた。都市か郊外か地方か、はたまた海外か、単純に「住む場所」に正解を求めない。幸せに生きるためには、人間的な「まち」への眼差しと、「まち」の魅力を的確に捉える感性を持つことが先。自分がどう捕まえるかで「未来のまち」は変わる、ともこの作品は語っている。(大西正紀さん)
JSCE賞
土木学会の審査メンバーで選出したJSCE賞は、以下の2作品です。
文化を自己決定する街(Yoichi 様)
コロナ禍で繋がりが弱くなってしまったこの時代で、まちでつながりを生むという内容が、非常に共感性が高い作品でした。デジタルが進展する中で、デジタルでのつながりとリアルのつながりの両方が求められていくこれからにおいて、リアルのつながりを生み出す新しい「まち」の姿として「効率」より「幸福」を求める主張に共感できました。
また、実際に行われている取り組みが紹介されていて、その暮らしを想像しやすい点もよかったです。
デジタル時代に目指す「まち」の姿とは【暮らしたい未来のまち】(yawaraishi 様)
工業高校の先生の視点で、普段、生徒と接する中で得た「暮らしたい未来のまち」という今回のコンテストテーマへの主張が、防災、自然共生、文化に根付いた、特に地方部における姿として、具体的かつ明快に表現されている作品でした。教師という立場から考えられたまじめな地方都市論で、こんな先生の教えを受けた生徒さんたちが、「暮らしたい未来のまち」をどうつくっていくのだろうと、将来に期待を持てる作品でした。
入賞
そのほか、以下の5作品が入賞いたしました。
生きものとしてのまち(HOKUTO 9×9 様)
都会だけではなく、田舎は田舎のまま新しい発展を目指してほしい(白咲夢彩 様)
時を超えて守る(よっさん 様)
もし道端にブロッコリーが落ちていたら(びしばし。 様)
ゆっくりと呼吸するまち(吉村 さま)
応募作品一覧
ご応募いただいた作品と、応募期間後に「#暮らしたい未来のまち」で投稿いただいている作品は、こちらのリンクでご覧頂けます。
コンテストは終了いたしましたが、これからも引き続き、「#暮らしたい未来のまち」の投稿をお待ちしております。


コンテストを終えて
今回のコンテストは、「コロナ後の”土木”のビッグピクチャー」の策定の一環として、広く市民の方々が思う「将来の物語・絵姿」を広範に、数多くうかがうことを目的に開催いたしました。お寄せいただいたそれぞれの物語から、未来の社会や暮らしを実現するために、インフラでできることはなにか、達成のために必要なインフラはなにかといったことを検討し、ビッグピクチャーに描き込んでいくこととしています。
コンテストハッシュタグ「#暮らしたい未来のまち」は引き続きnote上に残るため、これからの社会情勢や環境の変化などを踏まえた作品が、多くの方から継続して投稿されていくことを期待しております。
「ビッグピクチャー」は描いて終わり、発表して終わりという取り組みではなく、土木学会会員だけでなく、国民・市民の方々とともに、継続して「今」の先にある「未来」のことを想像し、未来のためになにが必要で、今何をしておくべきかを考える活動=ムーブメントとなっていくよう、引き続き取り組みをおこなってまいります。
コンテスト全体の寸評、審査員の皆さまからのコメントなどは、note公式ページに掲載されています。