現在地
【開催報告】土木学会誌2021年6月号にて、令和2年度「土木の日」活動報告が掲載されました!
全国規模で実施され盛会のうちに終了した、令和2年度の「土木の日」および「くらしと土木の週間」。
この度、土木学会誌2021年6月号にて、本部および各支部の「土木の日」活動報告が掲載されました。
詳しい内容は、下記ファイルをご参照ください。
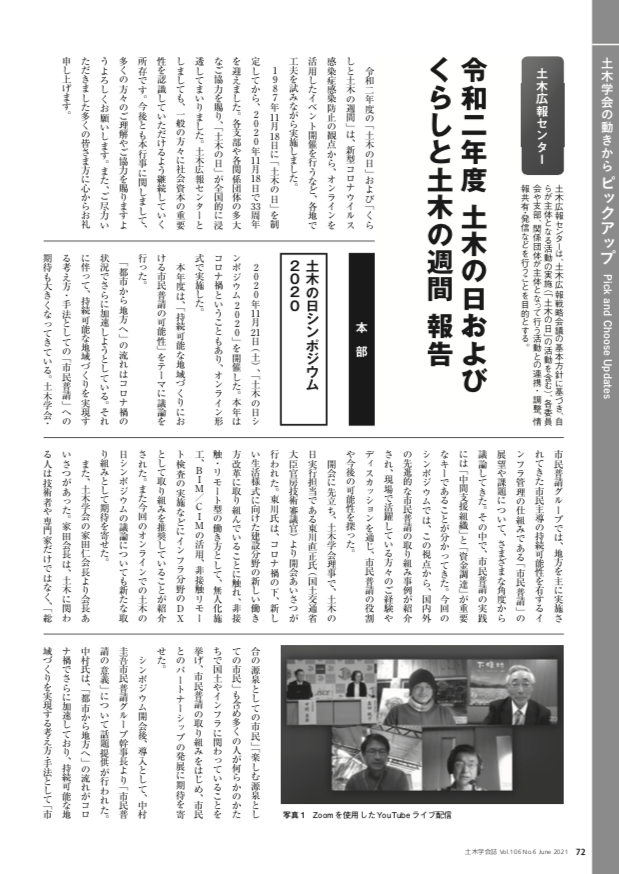
[令和二年度「土木の日」および「くらしと土木の週間」報告(土木学会誌2021年6月号)]
また、土木学会誌の誌面に掲載しきれなかった「土木の日シンポジウム2020」パネルディスカッションパートの報告記事(全編)をWebサイトで公開します!
【「土木の日シンポジウム2020」パネルディスカッション】
パネルディスカッションでは「持続可能な地域づくりにおける市民普請の可能性について」という内容で議論が展開された。
パネルディスカッションは、パネリスト5人(上原佑貴氏/宮島俊明氏/武田晋一氏/徳永達己氏(拓殖大学)/真田純子氏(東京工業大学)とコーディネーター中村圭吾氏に加えて、市民普請の事例紹介の参加者として西山穏氏(NPO法人しあわせみかん山/NNラントシャフト研究室)、清水淳氏(過去の市民普請大賞受賞団体/北川かっぱの会)で行われた。
三つの事例発表を受けての論点として、「(1)市民普請が機能するために必要な専門家、中間支援組織の役割」「(2)環境面に配慮した市民普請」「(3)持続可能な地域づくりに向けて」「(4)市民普請を始めるスタートアップの地域はどうすればよいか」などを中心に議論が交わされた。
(1)の「市民普請が機能するために必要な専門家、中間支援組織の役割」に関しての議論では、行政の役割は仕掛け人や裏方としての関与が重要であり、大学は、地域を学びの場として活用していくことで、修士論文や卒業論文の対象として大学生が地域づくりに参画できる機会を得るとそれぞれの役割について述べられた。また、地域、行政、専門家、企業、外部のボランティア等をつなぐ存在として、中間支援組織の役割が重要という認識が示され、地域づくりのスタートアップの際にも中間支援組織があることで、うまく仕組みとして定着するという初期段階での関与の重要性が述べられた。
(2)の「環境面に配慮した市民普請」としての議論は、しあわせみかん山の道普請を例に西山穏氏から行われた。本事例は、後継者がいなくなったみかん農地をNPOとして引き受け、自然と共生しながらみかんを生産し、その際の学びと交流を通じて1000年続く地域づくりを目指す取り組みである。西山氏からは手づくりで轍の部分のみ改良する耕作道の再生を例に、自然共生のため体と頭を動かしながら協働する取り組みが紹介され、環境配慮が参加を促す一つの動機付けになることも示唆された。パネリストからも環境に優れているのが市民普請であり、環境・持続可能性など新しい価値観を共有しながら進めることの重要性が示された。また、環境配慮など新しい価値観があることで大学も研究対象にしやすいとのコメントもあった。
(3)の「持続可能な地域づくりに向けて」の議論としては、関係人口の充実のための参加者間の交流環境を整えていくことの重要性が示された。徳永氏からは早川町の事例をもとに、大学生を無料で多人数受け入れ可能な「仕組み」や地域との交流の機会の充実など「仕掛け」などが整備されていることも持続可能な市民普請の重要なポイントであるとコメントがあった。また、宮島氏からは自分達の地域のことは自分達でつくるという地域への愛着の実感を持ってもらうことが重要と述べられ、自己意識の醸成についてコメントがあった。また、清水淳氏からは、持続可能な活動に関する視点として、時代に合わせて活動の重要視するものを変えていくこと(本会では、最初の10年は多自然(型)川づくり、後の10年は外来種問題)なども活動を活発に保っていく上で重要とコメントがあった。
(4)の「市民普請を始めるスタートアップの地域はどうすればよいか」という点についても議論がなされた。真田氏からは、石積み学校の事業を例に、誰でもできることをアピールすることや、技術を囲い込まない姿勢、SNSなどで絶えず情報発信など、初心者でも入り込みやすそうな企画者側の配慮・工夫の重要性が示された。また、関連して武田氏からは、タイでの市民普請のスタートアップを例に、成功事例(ノンコー村)がSNSを通じて技術者派遣を行うことで、インフラ整備需要に応えることや他地域への技術普及につながっていることが紹介され、SNSなどを通じた情報発信の重要性が示された。
これらの議論を通じて、①中長期に地域づくりを視野に入れた市民を巻き込む仕組みづくり、②徹底した地域資源の発掘と新制度とのマッチング、③コミュニティー力の評価指標による効果の把握、④住み続けたいという地域の愛着の醸成などが持続可能な地域づくりに向けたまとめとして挙げられ、持続可能な地域づくりについて、さまざまな視点から整理がなされた。
【担当】坂本 貴啓[国立研究開発法人土木研究所 水環境研究グループ 自然共生研究センター 専門研究員 / 土木広報センター 市民交流グループ 市民普請グループ]
| 添付 | サイズ |
|---|---|
| 3.82 MB |

