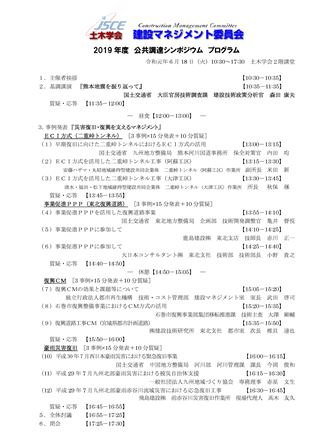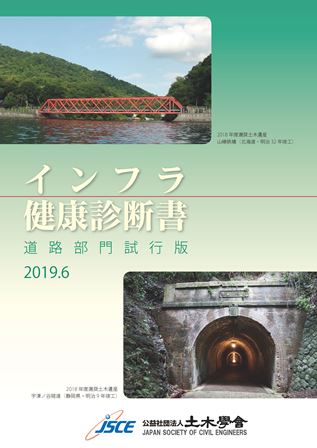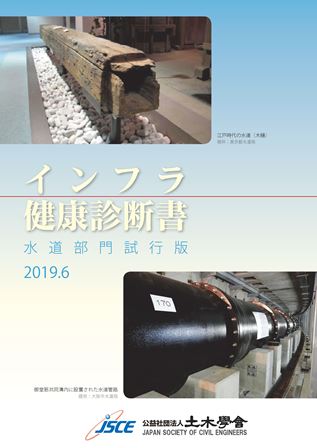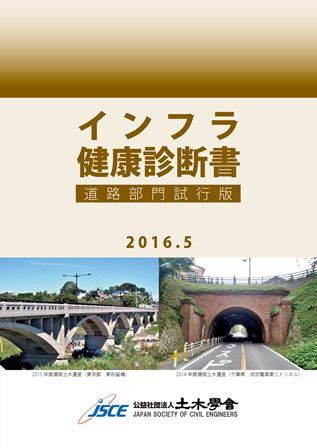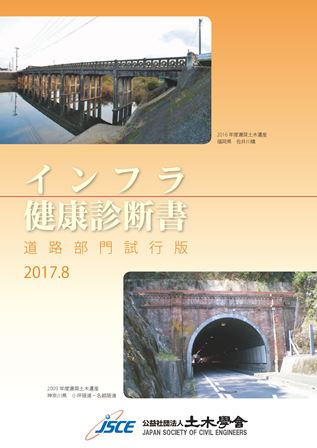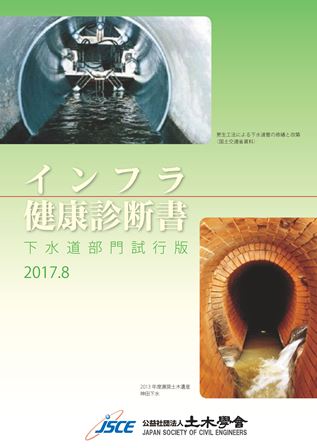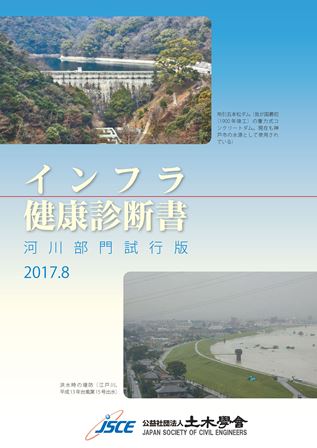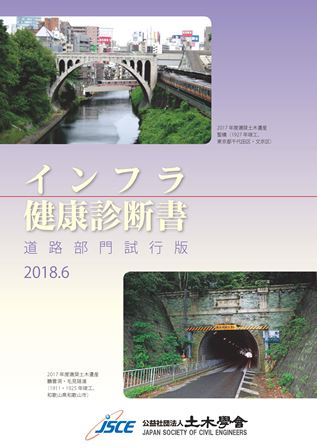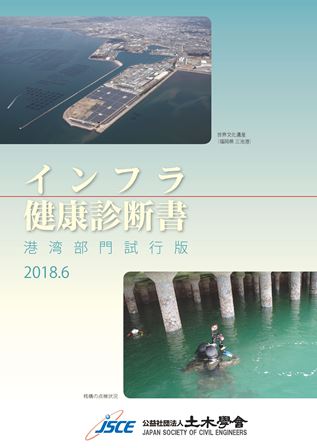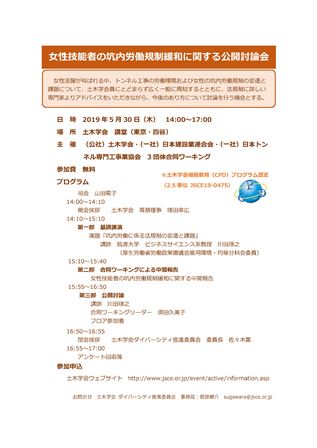公益社団法人 土木学会(会長 林 康雄)では、学会関係者やその家族、地域の方々、土木分野への進学・就職希望者など、多数の方を学会本部に招き、学会及び学会員が有する知見や技術、資料等を活用した「聞く」「見る」「触れる」体験の中で、『土木』の魅力を伝え、『土木』への理解を深めていただく場を目指し、2017年より「オープンキャンパス土木学会」を開催しております。
3回目の開催となる「オープンキャンパス土木学会2019」では、体験型プログラムの土木ふれあいフェスタをはじめ、特別企画展「1964東京オリンピック」、どぼくシアター、どぼクイズラリーなど、土木にご関心のある方も、無い方も、土木のおもしろさに触れ、さらに夏休みの自由研究としても活用いただけるよう、多彩なメニューを取り揃えております。小さなお子様から大人まで幅広く楽しんでいただける催しとなっておりますので、皆様のご来場お待ちしております。
記
日 時:2019年7月6日(土)10:30~16:00
場 所:公益社団法人 土木学会(新宿区四谷一丁目 外濠公園内)
参加費:無料
主 催:公益社団法人 土木学会 土木広報センター
後 援:東京都建設局 / 新宿区教育委員会
《土木ふれあいフェスタ》
夏休みの自由研究にもオススメ!



橋やトンネル、土砂崩れ、防災、環境など、多彩なテーマの実験・ゲームを豊富に取り揃えています。今年は、コンクリートを使ったアクセサリー作りやVR体験、水質パックテストなど、初登場のプログラムも盛りだくさん!
[実験・体験メニュー]※一部変更になる可能性もあります。
・かるたで土木のお勉強!(土木全般)
・VRで現場へGO!!(土木全般)
・アーチ橋模型(構造)
・重ねはり(構造)
・橋のつよさ実験(構造)
・トンネル実験~つよいトンネルのかたちは?~(トンネル)
・しらべてみよう!くらしの水(水道・環境)
・実験で学ぶ土砂災害(地盤・防災)
・コンクリートでアクセサリー(材料・コンクリート)
・ポケドボゲーム(防災)
《特別企画展 1964東京オリンピック》
オリンピックが土木にもたらしたイノベーション55年前(1964年)、国内初のオリンピックが東京で開催され、土木の世界にも多くのイノベーションを起こしました。オリンピックを支えた先人たちの功績や熱い想いを、土木学会が特別に集めた書籍や映像を通じご紹介します。

(昨年の企画展の様子)
《どぼくシアター》 ※一部変更になる可能性もあります。
映像でつなぐ土木の記録と記憶

土木学会では、1964年より、2年に1度、映画コンクールを開催しています。その受賞作品は、学会所有の貴重な映像資料であり、この中から選りすぐりのものをご覧いただきたいと思います。
[シアタープログラム]
10:45~「日比谷線建設記録 銀座の地下を掘る」
11:25~「東日本大震災、現場の戦い ~すべては被災地のために~」
13:00~「余部橋りょう さらなる100年へ」
13:25~「広域的なネットワークの形成に向けて 都市高速鉄道東京急行電鉄東横線(渋谷~代官山駅間)地下化の概要」
13:52~「夢は世界をかけめぐる ~海外技術協力のパイオニア~」
14:18~「未来に向けて~防災を考える~ ≪釜石の出来事≫」
14:53~「復興の道しるべ ~三陸鉄道北リアス線震災復旧工事~」
《どぼクイズラリー》
クイズにこたえてオリジナルグッズをゲット!

さまざまな実験やゲームを体験しながら、会場のあちらこちらに隠された土木にまつわるクイズにチャレンジし、土木学会のオリジナルグッズをゲットしよう!

(「オープンキャンパス2019」フライヤー)
【問合せ先】
公益社団法人 土木学会 土木広報センター 佐藤、小林
〒160-0004 東京都新宿区四谷一丁目外濠公園内
TEL: 03-3355-3448 E-Mail: cprcenter@jsce.or.jp