現在地
2025年度(令和7年度)土木学会全国大会「映画会」のお知らせ
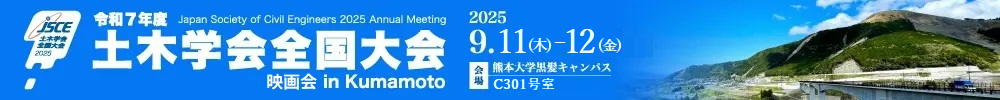
(2025.8.21)タイムテーブル及びCPD単位を修正いたしました。
(2025.8.18)CPD受講証明書発行に関する記事を公開いたしました。
(2025.7.14)CPDプログラムに認定、認定番号と単位を公開いたしました。
(2025.7.9)ポスター&タイムテーブルPDFを公開いたしました。
多数のご来場、誠にありがとうございました。
土木技術映像委員会では,全国大会期間中に映画会を開催いたします。これまでに収集・選定した記録映像の中から多くの優れた映像を上映いたします。
主催:土木技術映像委員会
会場:熊本大学黒髪北キャンパス 全学教育棟3F C301号室
開催日:2025年9月11日(木)、12日(金) 9:30受付 10:00開演
映画会は事前申し込み不要、入場無料です。
公共の交通機関にてお越しください。
駐車スペースはございませんので、自家用車でのご来場はご遠慮ください。
土木学会認定CPDプログラム
9月11日(木):JSCE25-0855 4.4単位
9月12日(金):JSCE25-0856 4.2単位
※単位は全作品視聴時のもので、ご視聴いただいた時間により変動いたします。
令和7年度全国大会 CPD単位について
2025年度(令和7年度)土木学会全国大会「映画会」におけるCPD受講証明書発行について
【2025年9月11日(木) 第1日目】
| 10:00 | 開会のご挨拶 土木技術映像委員会 | |||
| 10:05 | 39分 | 石を架ける-石橋文化を築いた人びと- | 各地に残る石橋を訪ね,見事な造形美を描くとともに,歴史やエピソード,構築技術,石工たちが託した夢,地域に与えた影響など文化遺産としての石橋の価値と大切さを訴える。 | 1996年 |
| 10:44 | 34分 | 海峡をつないだ技術-関門鉄道トンネル開通までの歩み- | 昭和17年に開通した世界初の海底トンネルである関門鉄道トンネルの完成までの歩みを,主に技術的な視点から物語風に紹介している。 難工事を克服した土木技術者の経験談や貴重な現場の映像を使い,トンネル工事の歴史を紹介する作品。 |
2003年 |
| 11:18 | 37分 | 【喜連瓜破 橋梁架け替え工事】二年半の軌跡 ~100年先を見据えて~ 工事担当者の想いに迫る! | 阪神高速では、2022年6月より14号松原線(喜連瓜破~三宅JCT)を終日通行止めの上、橋梁架替工事を実施した。 都市高速を長期間に渡って通行止めにするという前代未聞の工事の上、工事区間の直下には大阪市内でも有数の重交通を担う交差点があり、かつ周辺地域は密集市街地となっている。 制約条件の多い中、既設コンクリート橋桁の撤去及び鋼製橋桁の架設までを無事完了させ、2024年12月7日に約2年半ぶりに通行を再開した。 本動画は、工事着手前から通行再開までの事業の記録映像である。 |
2025年 |
| 11:55 | 25分 | 富士山を測る | 物語は昔から実施されてきた直接水準測量と,最新測量技術のGPS測量とで,富士山頂の標高を測ることである。 富士山の標高がどのような歴史的流れをしてきたか,資料を見せながら説明していき,富士山が直接水準測量で計測されたことがないことを強調している。また測量技術や器械の進歩が,より精密な測量へと変化していることを見せ,GPS測量については初歩的な説明にとどめている。教育関係機関だけでなく,広く一般の人も十分に楽しめる映画である。 | 1994年 |
| 12:20 | 休憩 | |||
| 12:50 | 35分 | アフガニスタン 用水路が運ぶ恵みと平和(技術編) | 本作品は本編「緑の大地計画の記録(2002~2015)」(30分)と技術編「PMSの灌漑方式」(35分)からなる。今回は技術編を上映。 技術編は、運河の建設に現地で得られる資材や建設機械、技術水準を考慮し、近代工法ではなく、日本で行われていた伝統工法を採用し、水路を蛇篭で固めたり、大河クナール川から運河へ取水するために鉄筋コンクリ―ト造りの堰ではなく、福岡県朝倉市にある石造りの山田堰をモデルにしたこと、また畑に水を汲み上げるのにやはり朝倉市の三連水車をモデルとして採用したことなどを、イラストも使用して分かりやすく解説している。現地の状況に合わせた工法を採用することが必要なことを示唆している。 土木の目的は何か?現実的で賢明な工法の採用とはどういうことか?を暗示する、良い作品であり、土木を志す学生、若い土木技術者たちに是非見て欲しい作品である。 |
2016年 |
| 13:25 | 21分 | 令和のリニューアル 北陸自動車道 米山トンネルのインバート補強 | 北陸自動車道の米山トンネル下り線は建設以来、盤ぶくれによる路盤の変状が進行していた。本作品は、令和3~4年度に行ったインバート補強による補強対策工事の記録を映像としてまとめたものである。 | 2022年 |
| 13:46 | 36分 | つなぐ~三角大矢野道路「天城橋」建設の記録 | 地域高規格道路「熊本天草幹線道路」の一部を構成し、熊本県上天草市と宇城市をつなぐ「天城(てんじょう)橋」は、平成30年5月20日に開通しました。天城橋は、橋長463m、アーチ支間長350m、アーチ橋としては国内2位、ソリッドリブ形式のアーチ橋としては、国内で1番の長さを誇る長大橋です。当記録映像は、平成26年秋から始まった橋梁本体の架設工事の様子を、平成30年5月の供用開始まで捉えたものです。 | 2018年 |
| 14:22 | 32分 | 日本初の地下鉄建設 | 東京に地下鉄を造る…その夢を実現するため、多くの土木技術者が「一致協力」して完成(昭和2年(1927年)12月30日開業)した日本初の地下鉄。その第1歩は、今の東京メトロ銀座線、上野・浅草間2.2キロの建設から始まりました。この作品は、当時の建設工事を記録した貴重な無声映画、「東京地下鐵道工事乃実況」をデジタルリマスターし、工法の解説や、建設に携わった技術者の紹介を盛り込んだ建設記録映像で、一般の方にも親しみ易い内容となっています。 | 2017年 |
| 14:54 | 1日目 終了 | |||
【2025年9月12日(金) 第2日目】
| 10:00 | 17分 | 人々の暮らしを取り戻す 精鋭たちの総力戦~2016-2021 熊本県南阿蘇村-技術者たちの闘い | 平成28年(2016年)に発生した熊本地震。最大震度7を記録し甚大な被害をもたらした。 本作品は阿蘇大橋付近で発生した大規模な斜面崩落からの復旧や復興のシンボルでもある「新阿蘇大橋」開通に向けて立ち向かう土木技術者達の記録である。 震災直後から現地に入り、余震の不安の中で応急調査。その後、限られた時間の中で、技術を結集し地盤調査設計、橋梁設計を完了させる。その力の根源は、“人々の暮らしを守る”という技術者の「使命感」であった。 国民の暮らしを守るという使命感を持った技術者達の挑戦を描いている。 |
2025年 |
| 10:17 | 37分 | 青函トンネル | 本映画は青函トンネルの歴史と,そのトンネルがいかにして掘られたか,その調査・工事の全工程を多くの現場でのフイルムの中から編集し総集編の形で紹介した記録映画である。土木工事の単なる施工記録としてのみならず,一般向けの映画としても深く感銘を与える作品。 | 1985年 |
| 10:54 | 44分 | 復興の道しるべ-三陸鉄道北リアス線震災復旧工事 | 本映画は、鉄道・運輸機構、鉄道総研、東急建設JVの土木技術者が、東日本大震災で甚大な被害を受けた三陸鉄道北リアス線の一日も早い復旧に向けて想いをつなぎ、「目に見える復興のシンボル」となるGRS一体橋梁を完成させ、北リアス線全線再開を通じ、被災された三陸沿岸の人々を力づけた奮闘記録です。 一般市民の方々に土木技術者の役割を伝えるため、通常の工事記録映画とは異なるドキュメンタリー映画の手法を用いた記録映像です。 |
2018年 |
| 11:38 | 16分 | 石橋のふるさと-肥後の石工を訪ねて | 肥後の石工により手がけられた熊本県内の石橋の紹介と歴史に触れ、さらに木橋に代わり盛んに石橋が掛けられた理由及びその工法などを中心に紹介する作品である。御船川目鑑橋、零台橋、通潤橋などを通し、支保工や水切りなどの工法の解説を行い、石工集団の成り立ちの過程や明治維新後の活躍、橋架橋のスポンサーでもある惣庄屋の存在などについても触れている。撮影当時県内に現存した石橋の映像も可能な限り収められているようであり、中には橋の架橋年代等不明のものまで含まれている。 | 1988年 |
| 11:54 | 20分 | 阪神・淡路大震災による道路の被災と復旧 | 被災後の応急復旧措置から幹線道路の本格復旧に至るまでの耐震設計を見直しての構造物補強,ゴム支承を使用した落橋防止工法等の施工状況を詳細に紹介。 | 1995年 |
| 12:14 | 休憩 | |||
| 12:45 | 24分 | 余部鉄橋の記憶 永久保存版 | 建設当時東洋一の規模を誇り,今日まで山陰地方の大動脈として役割を果たしてきた山陰本線余部鉄橋。その工事完成までの歴史,錆との闘い,季節ごとの雄姿等の貴重な映像を収録。 | 2007年 |
| 13:09 | 58分 | 日本の近代土木を築いた人びと | 近代土木の黎明期に国土開発の出発点となった土木技術の自立に挑んだ5人の若き技術者を紹介。鉄道の井上勝,琵琶湖疏水工事の田辺朔郎,総合土木の古市公威,河川の沖野忠雄,港湾の廣井勇 | 2002年 |
| 14:07 | 25分 | 繋げる~赤い鉄橋を蘇らせた工事の記録~ | 上田電鉄別所線の千曲川橋梁は大正13年に建設されました。かつて青木村や真田町・丸子町など5線を結んでいた上田電鉄も今では唯一別所線だけが残り、一時は廃線の話もあった路線ですが地域からの応援もあり通勤や通学、観光の足として愛されてきました。 2019年10月東日本、台風19号の被害を受けその千曲川橋梁が落橋。災害を受け廃線となる地方鉄道も存在する中、上田電鉄別所線は地域の熱い期待と応援、各所の支援を受け復旧が決定しました。 この映画は532日の月日をかけ、鉄橋を蘇らせた工事の記録です。一般的な工事は事前に検討・計画・設計を十分に行うのに対し、今回手元にある資料は約100年前の設計図のみだったため、社内でチームを組んで組織力を生かし、最新のデジタル技術である3Dレーザースキャナー 、3Dcadスケッチアップ、360°カメラなどを活用して工事が行われました。 早期復旧に向け、取り組んだ当社の土木技術者の活躍、デジタル技術の活用の様子、設計・計画を含めた建設技術者の仕事や、インフラ建設に携わり技術力やマネジメント力を発揮する建設の仕事についての想いも表現されています。今後も起こりうる様々な災害に対し、当社の果たすべき役割や存在価値を再認識し、自然と対峙しながら復旧を行う建設の魅力を伝える作品となっております。 |
2022年 |
| 14:32 | 閉会のご挨拶 土木技術映像委員会 | |||

