現在地
令和元年度 出版文化賞受賞作品
令和元年度 土木学会出版文化賞は以下の3作品に決定いたしました。※著者名50音順
立体交差 ジャンクション
大山 顕( おおやま けん)著
株式会社 本の雑誌社 2019年刊
 |
|
【受賞理由】
本書は、団地や工場など、日常的ではあるがよく眺めると奇妙ともいえる風景の撮影に定評がある写真家の写真集であり、全国各地の高速道路のジャンクション、インターチェンジが被写体である。巻末のエッセイでは、現代の風景に対して、立体交差という観点から著者独自のユニークな考察が展開される。
見開き全体に広がる写真は高精度で迫力があり、巨大構造物のスケール感や立体交差の幾何学的な複雑さ、立地環境の多様性などを余すことなく表現している。ほとんどの写真は身近な視点からの撮影で、それらが昼や夜、施工中などの大まかなまとまりを持って掲載されており、ページを繰る体験は良質な映画(ロードムービー)を鑑賞しているようである。
一方で、批評性も高い書籍でもある。著者によると、立体交差は異なる交通モードの衝突を解消するために生まれた構造物であり、その結果、その造形、特に私たちが日常的に眺める構造物の裏側には、都市を支えるための機能や立地する地形、あるいは歴史的経緯までもが直接的に現れる。このような視点は、我が国の都市景観全般に対して重要な論点を提供するだろう。
本書は、土木技術者から一般読者まで広く開かれた書籍として、日常的ではあるが主題化されることが少なかった立体交差に新しい光をあてると同時に、鑑賞後の余韻として、土木工学に関する様々な視点や議論を喚起する書籍である。よって、ここに土木学会出版文化賞を授与する。
図解 誰でもできる石積み入門
真田 純子(さなだ じゅんこ) 著
農山漁村文化協会 2018年刊
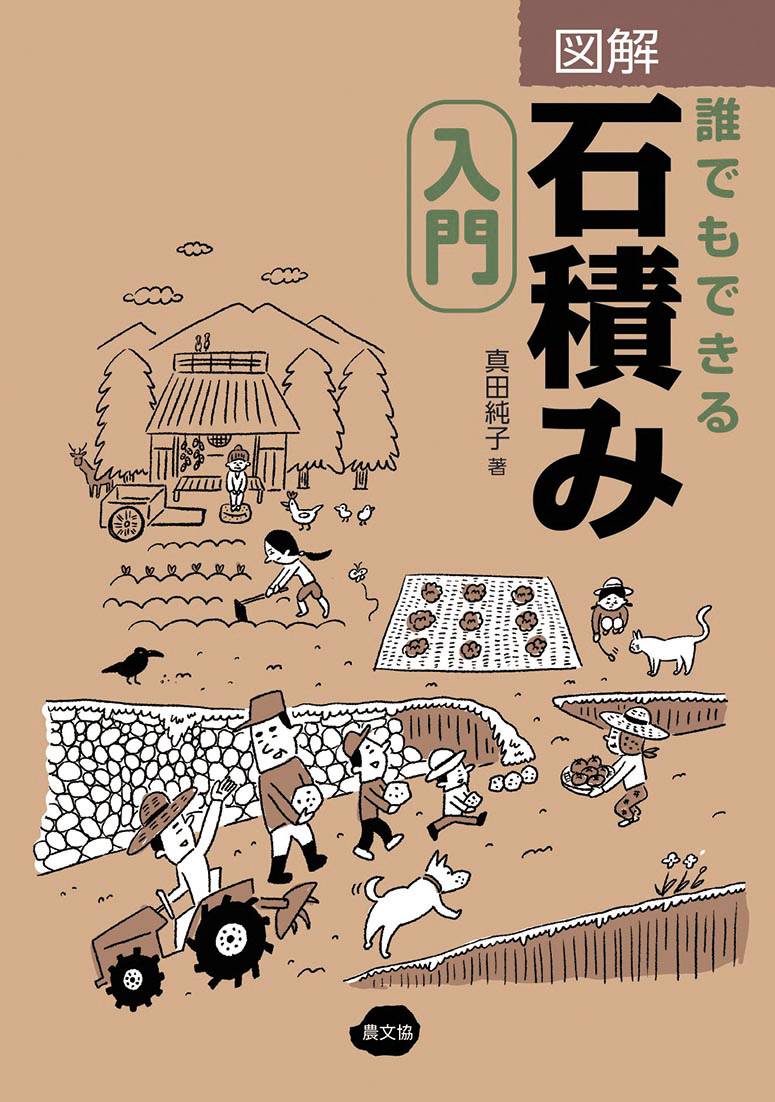 |
|
【受賞理由】
棚田や段畑に用いられている石積みの壁は、日本人なら誰しも一度は実物を間近に見た、あるいは写真やビデオ映像で見たことのある、伝統的な土木構造物である。しかしながら、それがどういうものであるかを、詳しく観察したり深く考えたりしたことのある人は、意外と少ない。
本書は、石積みに出会った著者が、自らの体験に基づき、その素晴らしさを広く伝えようとしたものである。「そもそも石積みとは何か」という話から始まるが、ふんだんなカラー写真によって本書の全貌をつかむことができ、すぐさま読者を高揚させる。それに続く、特有で伝統的な道具、床掘り、石の置き方や積み方の説明は、イラスト、写真、ケーススタディ、コラムもあって、土木の知識のない人にも親しみやすい。まるで石を一つずつ積みあげていくかのように丁寧で、漏れもなく、工事の安全性や効率にも触れている。積み石のかみ合わせやグリ石の層による排水など、構造や地盤の専門家もうなずく講義もある。結びの部分には特に、著者の思いがこめられている。石積みとの出会いに始まり、石積み学校での経験、日本やイタリアの石積みの現状が綴られ、これらは本書の余韻となる。
以上のように本書は、石積みの文化や景観の素晴らしさを広く啓蒙し、土木の原点を再認識させるものであり、これから実際に石積みをしようとする人にとっては数少ない示方書のような価値もある。よって、ここに土木学会出版文化賞を授与する。
ダムと緑のダム 狂暴化する水災害に挑む流域マネジメント
虫明 功臣(むしあけ かつみ) ・太田 猛彦(おおた たけひこ)監修
株式会社 日経BP 2019年刊
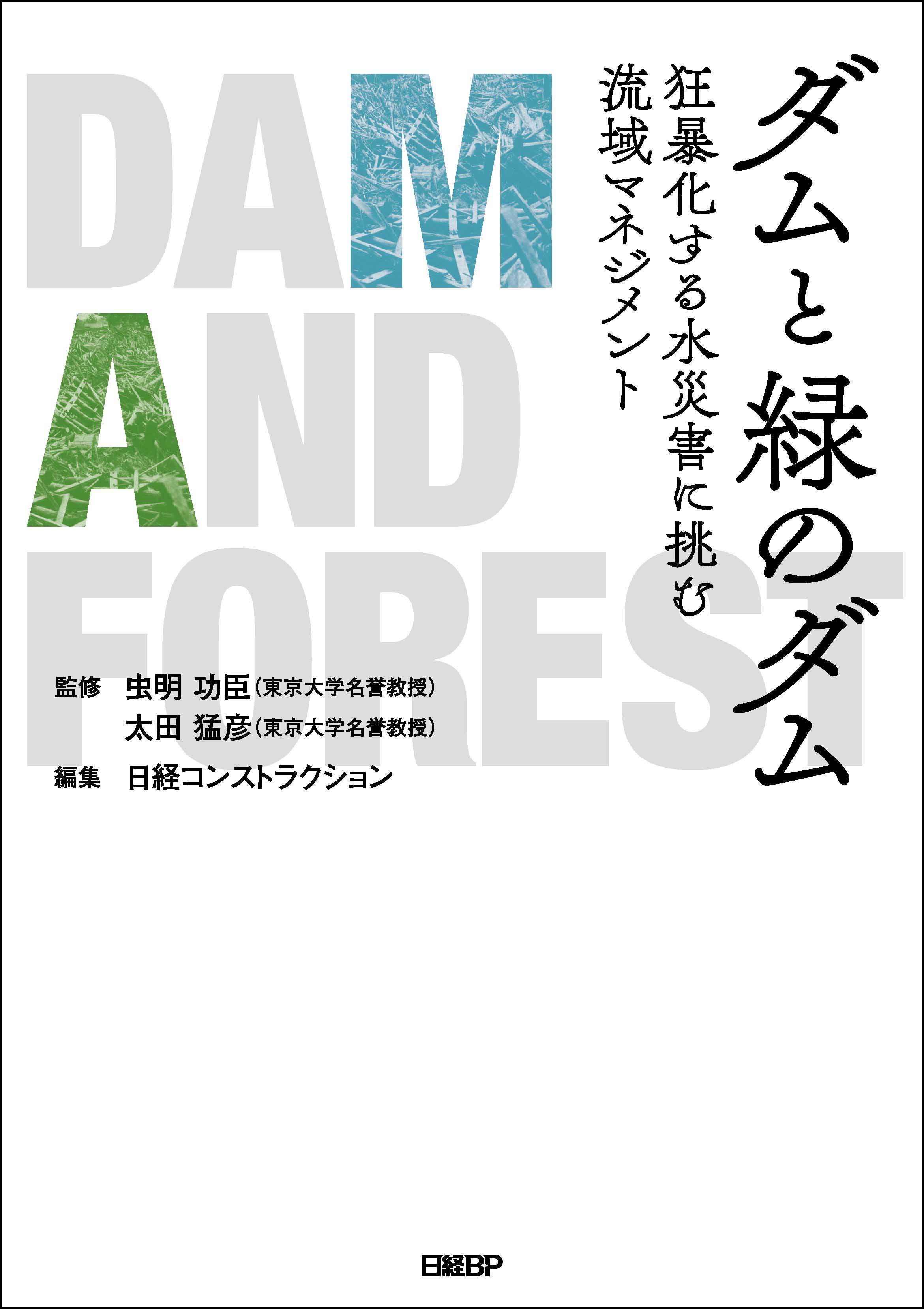 |
|
【受賞理由】
本書は、気候変動により規模が大型化し、頻度も増加すると見込まれる水災害に関して、河川の上流域に焦点をあてて多面的に論じている。河川上流域での大規模広域豪雨に伴う洪水・土砂・流木が一体となって流出し、被害を拡大する「複合型水災害」に対して、ダムと森林の役割や機能をそれぞれ検証し、問題点も明らかにした上で、ダムと森林が一体となった流域マネジメントの必要性を説き、水循環マネジメントへも言及することで、直面する課題解決への総合的な展開の必要性を喚起している。
各地の水災害事例を取り上げて、土木工学や農学における、森林、ダム、砂防、水文の専門家が、それぞれの分野の現状や役割、課題について、多くの図版も用いてわかりやすく述べており、ダムか森林(緑のダム)かと、これまで二項対立的に議論されてきた課題に対して、どちらか一方に立つ論述ではなく「ダムと森林が手を組む」という主張をしている。様々な意見がある現状に対して、科学的視点から冷静な理解を促す内容となっている。
直近となる2019年までの水災害事例を取り上げており、非常に時宜を得た書籍であるとともに、歴史的、国際的な視野から必要な情報が整理されて提供されており、流域全体を対象とした水災害マネジメントと水循環マネジメントについて学ぶものにとって有用な書籍として、土木工学の発展に寄与するものであると評価される。よって、ここに土木学会出版文化賞を授与する。




