現在地
新しいコメントの追加
コメントする上での注意事項
- 投稿後に修正できませんので、プレビューボタンを使って間違いがないか確認してください。
- コメントは内容確認のうえ、掲載されます。投稿後に即公開はされませんのでご了承ください。
- 寄せられたご意見の内容が記事の範囲を逸脱する等、適切でないと判断された場合は公開されません。
- ご投稿いただいた記事の誤字脱字、不適切と判断された部分を削除する等の修正を加えることがあります。あらかじめご了承ください。
【Web版第21回】 飛騨トンネルが地域連携の風穴を開ける~難工事を克服した技術者の決意と挑戦~

川北眞嗣氏
新技術への挑戦、不良地山や大量湧水との格闘を繰り返す難工事…20世紀最後の大規模プロジェクトといわれた飛騨トンネルに正面から向き合い、トンネル工法や施工計画の検討から現場指揮まで一貫して担当し、東海地方と北陸地方の地域連携に大きな成果をあげたトンネル技術者の取り組み。
■■東海北陸自動車道の最難関・飛騨トンネル
東海北陸自動車道は、平成20(2008)年7月に全線供用された高速自動車国道です。この東海北陸自動車道には、飛騨清見ICと白川郷ICの間に位置する籾糠山(もみぬかやま)を貫通する、国内道路トンネル第二位の長さ(10.7km:完成時)を誇る飛騨トンネル(岐阜県飛騨市・白川村間)があります。20世紀最後のビッグプロジェクトと呼ばれたこの難工事に正面から向き合い、施工計画の検討から現場指揮までをトンネル技術者として担当されてきたのが、川北眞嗣さんです。
■■TBMへの挑戦

写真-1 直径約13mのTBM(tunnel boring
machines)(写真:NEXCO中日本)
飛騨トンネルの工事を語る際に忘れてならないのは、道路トンネル工事において一般的であったNATM工法ではなく、TBM採用というトンネル技術革新への果敢な挑戦です。高速道路の建設期として多くの大事業を抱えていた当時は、トンネル施工においても、新技術を積極的に採用する気概に満ちていたそうです。とはいえ、国内有数の長大トンネル、最大土被り1,000m強、先行トンネル事例がない未知の籾糠山、国内初採用の大断面TBM、しかも片押し掘り…これら全てが新しい挑戦でした。
川北さんと飛騨トンネルの出会いは、起工1年前の平成7年のこと。日本道路公団(当時)本社で新技術開発部門のトンネル担当として施工計画に参画し、その後工事を所管する名古屋支社において、仕様書や技術基準などが何も存在しない大断面TBMの施工計画策定や工事発注作業に取り組みました。
TBM採用に関して当時は「本当にやれるかといえば不安だった」と語る川北さん。「いくら知識があっても現場でTBMを動かしたことがない」とその理由は明快です。そして「トンネルは特に現場を見続けるべき、だから現場にとにかく通え、と言われた先輩の教えは自分も引き継いでいる」そうです。
■■1mでも前に

写真-2 湧水帯では最大毎分15トン以上の
水と格闘(写真:NEXCO中日本)
川北さんは、平成14年4月から飛騨工事長として施工に関わります。この時すでに工事発注から5年以上、先進坑のTBM発進から4年以上が経過し、工期短縮の期待を背負っていたTBMは何度も籾糠山の不良地山に足止めを食らわされていました。それでも川北さんは、計画段階で得たノウハウと5年以上蓄積された現場データを背景に「うまく使いこなせばTBMは間違いなく有効だ。よしやってやるぞ」と心待ちにしていたそうです。しかし着任直後から川北さんを待ち構えていたのは、不良地山に加えて大量湧水との格闘…採掘面はまるで滝壺さながらの、文字通り切羽詰まった状況でした。日に日に変化する現場を自分の目で確認し、即時に判断・指示するために、川北さんは現場に通いつめます。「こんなに現場に詰めることが出来て技術者冥利に尽きる。でも四六時中、現場用の携帯電話がいつ鳴るかいつ鳴るかと気が気じゃなくて…」と当時の心境を振り返ります。

写真-3 不良地山に拘束されるたびに人力で
TBMを救出(写真:NEXCO中日本)
「飛騨トンネル工事は、想定外の不良地山が一体どれだけ続くのかがわからなかったのが厳しい」と川北さんは振り返ります。工期延期に加えて、当初予算の超過、さらには道路公団民営化の議論が起こるなど世間の風当たりが強まっているという感覚も肌身に感じ、川北さんをはじめとした工事関係者はみな、工事が順調に進まないこと以上の漠然とした心労を抱えていたとのことです。そんな中でも川北さんは、現場工事長として「とにかく前に掘り進むことだけにベストを尽くす」という日々の努力目標を掲げてモチベーション確保に努めました。
■■ハイブリッド工法に先鞭
当初計画した「TBMでの片押し貫通」は断念(「迎え堀り」で工期を挽回)したものの、飛騨トンネルでは結果的に先進坑の6割、本坑の4割をTBMで掘削しました。「これはTBMの著しい成果だ。特に大量湧水にはTBMでないと対応できなかっただろう」と川北さんは振り返りますが、「飛騨トンネルクラスの現場をTBMのみで貫通出来ることはあり得ないだろう」とも続けます。そして今後最も有望な工法の見通しについて、「ハイブリッド…つまり条件に応じてTBM、NATM、シールド工法等を組み合わせ施工していくことです。飛騨トンネル工事でも、当初から工法をもっと臨機応変に切り替えられるような施工計画を立てていれば、より効率的にトンネル工事を行うことが可能だったはず」と川北さんは慢心せず技術面での総括を語られました。
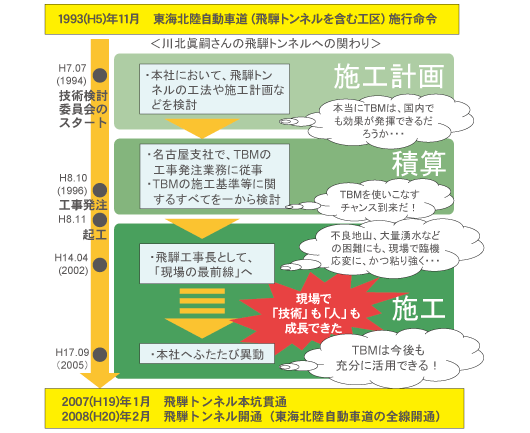
図-1 飛騨トンネル工事の流れと川北氏の思い・考え・行動
■■ついに貫通・全線開通
川北さんが異動に伴い現場を離れて1年半後に本坑が貫通、そしてさらに1年後ついにトンネル区間が開通し、この日をもって東海北陸自動車道は全線開通となりました。現場で全線開通を迎えなかったものの、この日についてはやはり特別な感慨を持たれたそうで、「やるだけやった感はあったけど、現場を離れるのはさすがに後ろ髪を引かれた」とのことです。ここでは紹介しきれないほど数々の筆舌に尽くしがたい困難に直面した飛騨トンネル工事でしたが、工事期間中誰一人として犠牲者を出しませんでした。これも施工安全性の高いTBMの大きな成果といえます。
飛騨トンネルによって、地域間移動が活発化したのみならず、地元住民の生活圏や通学先選択肢の拡大、観光客の増加など、東海・北陸地域のさらなる地域連携促進効果も生まれています。こういった話こそトンネル技術者冥利に尽きる、と川北さんは言います。「下宿せずに通えるようになったという地元高校生の声を聞くと、工事をやりきって本当に良かったと思うね」と目を細めます。
■■難工事によって自らも成長

写真-4 避難坑貫通時の工事区メンバー
(前列左端が川北氏)(写真:川北氏)
トンネル工事における不測の事態やトラブルを逞しく切り抜ける原動力は、「最後は技術よりも人の持つ力や知恵や経験が大事」であり、「私自身も幾多の壁を乗り越えることで成長できたと思う」と力を込める川北さんの言葉が印象に残ります。川北さんは現在、15本のトンネルを有する舞鶴若狭自動車道の建設に携わる敦賀工事事務所長。「今回こそは開通時にここに居てもいいかな」と語る笑顔のなかに、日本の道路トンネル施工技術を支える自信と誇りを垣間見た気がします。
川北眞嗣さんに聞きました!
――トンネル技術者になられたきっかけや動機は?
日本道路公団入社後の現場が関越トンネルで次が東京湾横断道路、もうその頃には「トンネル分野を究めないともったいない」と思っていましたね。知れば知るほど面白いですよ。
――飛騨トンネルの工事現場の雰囲気はどうでしたか?
トンネルはとにかく貫通が最大かつ唯一のテーマです。何としても貫通させる、という意地と信念がモチベーションを支えました。籾糠山という強敵相手の難工事だったからか、工事関係者全員が強い団結力で目標を共有できた現場でした。
――それでは技術者の皆さんにメッセージを
大規模プロジェクトに参画する機会があれば逃げずに挑戦して下さい。そしてそこで培った技術や知恵を、身近な生活シーンで活用できないかも常に考えてみて下さい。「コンクリートから人へ」転じて「コンクリートから生活シーンへ」かな。
行動する技術者たち取材班
森島仁 Hitoshi MORISHIMA 日建設計 企画開発部 主管
参考文献
2012.5.22
| 添付 | サイズ |
|---|---|
| 269.08 KB |
