現在地
新しいコメントの追加
コメントする上での注意事項
- 投稿後に修正できませんので、プレビューボタンを使って間違いがないか確認してください。
- コメントは内容確認のうえ、掲載されます。投稿後に即公開はされませんのでご了承ください。
- 寄せられたご意見の内容が記事の範囲を逸脱する等、適切でないと判断された場合は公開されません。
- ご投稿いただいた記事の誤字脱字、不適切と判断された部分を削除する等の修正を加えることがあります。あらかじめご了承ください。
【Web版第15回】 技術を育み公道展開、そして生活空間へ~ITS黎明期の技術開発をかたちに~

天野肇氏
いまや快適なカーライフに欠かせないETC…その第一歩は、工場のFA技術を用いた海外での公道実験にあった。新しいことに積極的にトライする精神を大切に、技術力とマネジメント力の両輪を駆使してITS普及を楽しく牽引。
■■様々な立場からITS黎明期を支える
ITS(Intelligent Transport Systems:高度道路交通システム)は、すでにカーナビやETC、バスロケ等で利用できるだけでなく、今後の社会変革につながる技術としても期待されています。今回は、前身のVERTIS含め設立16年以上であるITS Japanの専務理事であり、黎明期よりITSを立ち上げ、技術開発と普及に向けて官民調整の仲立ちをしてこられた天野肇氏を紹介します。
■■技術を一歩、外へ

写真-1 シンガポール公道実験での
ERPゲート(写真:天野肇氏提供)
天野氏とITSのつながりは、ITSの幕開けにあたる1980年代であるトヨタ自動車(株)社員時代に遡ります。大学時代より精密機械工学を専攻し研究してきた天野氏は、入社当初はロボット技術によるFA(Factory Automation)に携わります。その後、工場でのセンサー技術や画像処理技術に関する知見を認められ、RFID技術(無線チップによる人・モノ・クルマ等の識別技術)を活用したETCの開発に携わることになりました。そして公道での実験に多大な調整労力を要する日本に強くこだわるのではなく、海外に活動の場を求めていくことになりました。

写真-2 シンガポール公道実験スタッフ(写真:天野肇氏提供)
最初の公道実験はシンガポールでのERP(Electronic Road Pricing)課金実験。それまで相手にしてきた工場ラインとは全く勝手が違いました。工場内を分速5m(時速0.3km)で移動する部品ではなく、時速60km以上で走行する車両を認識する技術革新が必要で、そのうえ「善人ばかりが使うわけでなはない環境」(天野氏談)を想定しなければなりません。天野氏は地元関係者も巻き込んだ参加型開発をすすめ、やがてシンガポール政府の信頼を得ていきます。
トヨタで最初に関与したFAの知見と経験がETC開発に大いに役立った、と天野氏は語ります。経済成長期に培ったスムーズな部品調達や製品輸送を行うための工場内管理技術を、公道に適用すべく技術革新を図ったことが、いまのETC開発の土台となりました。
■■公道実験で技術も人も成長
シンガポールに続き、プロジェクトリーダーという責任ある立場で天野氏が取り組んだのは「中国ETC実験」(返還前の香港と広州)です。当時、中国共産党に対する配慮が極めて重視され、労働習慣や文化の違いに大いに苦労したそうですが、「寛容なルール下で、思い切った公道実験を展開出来たのは大きな魅力」(天野氏談)でした。

写真-3 杭州ETC公道実験のようす
(写真:天野肇氏提供)
また同時期、豊田章一郎会長(当時)より、海外のITS事業に際し「ITS担当はモビリティ面での社会貢献とは何かを全面に考えればよい…(君がやってもどうせ儲からないから)」というユーモアあふれる薫陶を天野氏は直接受け、入社時からずっと漠然と考えていた「誰かの幸せのために働く」という価値観に明確な方向付けをいただいたと感じたそうです。そのため、経済的リスクをはじめとする海外での様々な困難に対し、「可能性がありそうなら新しい技術に積極的にトライする精神」を常に大切にすることができたと天野氏は振り返ります。
■■官民共同開発を仲立ち

写真-4 実験現場で関係者とコミュニ
ケーション(写真:天野肇氏提供)
1994年、ITS分野の活動が本格化すると天野氏は、技術者としての豊富な経験を活かし、技術とマネジメントの両方を知る貴重な人材として、国産のDSRC(Dedicated Short Range Communication:スポット通信)技術の国際標準化やITS関係者の総力結集をすすめます。その後、ITバブルが終焉を迎えつつある逆風下でも、企業のモチベーションを上手く引き出してボランタリーな技術開発を継続し、関係者一丸となって国際標準化を推進していきました。さらに「開発技術をみんなに見てもらおう」という意識を関係者で共有し、「ITS世界会議2004愛知・名古屋」のショーケースや「スマートウェイ公開実験デモ2006」をコーディネートするなど、ITSをとりまく環境やご自身の職能が変わっても天野氏はバイタリティを発揮し続けました。
このようなITSの技術は、高速道路網におけるETCだけでなく、駐車場のノンストップ自動決済、ITS車載器への情報配信など、まちなかのITSスポットとして、これからもさらに私達の身近な生活シーンに導入されていくことでしょう。
■■技術者も一歩、外へ
自動車のハンドルと同じように「遊び」があるからこそ発想にゆとりが生じる…こんなたとえ話を引用しながらおっしゃられた「技術者ひとり一人が、先行き不透明な今だからこそ『志』を強く持ち、個人の能力を外で『せっかくだから試してみよう』という気概を持つことが大切」…これが取材でいただいた天野氏からの強いメッセージです。
そしてその過程で、様々な技術やノウハウ、モチベーションを有する仲間達とのチームワークづくりの大切さを天野氏が強調されていたのが、取材で大変印象に残りました。
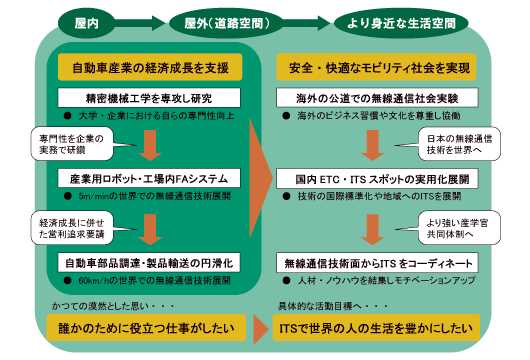
図-1 天野氏の活動や考えと日本のITS(DSRC技術)の展開
天野肇さんに聞きました!
――公道実験のマネジメントを行うコツはあるのですか?
自分の適正は「まとめ役」だと思っています。だからオモシロイ考え方を持っている人と繋がる機会を逃さないことと、「現実的」な視点を常に頭の中に残すことも意識しています。
――現実的な視点・・・ですか?
言い換えれば、「出来そうなことを探し」それを「出来そうな人を大切にする」のと、「やりたいことを咀嚼して技術者と共有する」ことが大切です。また、そのなかから「アピールポイントを抽出して常に情報発信」するのも重要です。情報を発信しているからこそ「瓢箪から駒」的にアイデアや協力者が現れるかも知れませんしね。
――それでは若い技術者の皆さんにメッセージを
仕事でも余暇でも、積極的に外出して活動を拡げて欲しいですね。机の前や家の中で視野を拡げようといっても限界があるでしょう。若い人達は本当に能力(英語力にしても情報収集力にしても)が高い、だからそれを前提に、自分をどうやって活かせるかについてさらに考えて行くことが大切だと思います。
行動する技術者たち取材班
森島仁 Hitoshi MORISHIMA 日建設計 企画開発部 主管
参考文献
1)「日本のITS」(2010年6月、ITS Japan編)
2011.6.3
| 添付 | サイズ |
|---|---|
| 267.31 KB |
