現在地
新しいコメントの追加
コメントする上での注意事項
- 投稿後に修正できませんので、プレビューボタンを使って間違いがないか確認してください。
- コメントは内容確認のうえ、掲載されます。投稿後に即公開はされませんのでご了承ください。
- 寄せられたご意見の内容が記事の範囲を逸脱する等、適切でないと判断された場合は公開されません。
- ご投稿いただいた記事の誤字脱字、不適切と判断された部分を削除する等の修正を加えることがあります。あらかじめご了承ください。
【Web版第7回】 「ローカリズム」の実践を世界で ~災害多発国 日本からの技術的貢献~

竹内邦良氏
災害多発国である日本の災害対策の経験や知識・技術を世界各地の防災に役立てるため、世界唯一の水災害機関ICHRAMの日本国内での設立に尽力され、現地の人が自らの経験や地域の実態に即した仕組み・やり方に気づき、取り組むための教育プログラムと人的ネットワークを構築。
ユネスコは、諸国民の教育、科学、文化の協力と交流を通じて、国際平和と人類の福祉を促進することを目的とした国際連合の専門機関です。そのユネスコの趣旨にそって、途上国のエンジニアが、短期・長期で用意されたプログラムにより、水災害に関する知識や情報を学ぶ機関が国内にあります。
水災害・リスクマネジメント国際センター、通称ICHARM(アイチャーム:International Centre for Water Hazard and Risk Management)は、世界の水関連災害を防止・軽減するため、各地域の実態をふまえた的確な戦略を提供し、その実践を支援する世界拠点として、茨城県つくば市に2006年3月に開設された、世界で唯一のグローバルな水災害センターです。
ICHARMが進めるこの技術的国際貢献に重要な役割を果たしている一人の技術者がいます。ICHARM初代センター長の竹内邦良氏です。
■■ローカリズムの実践
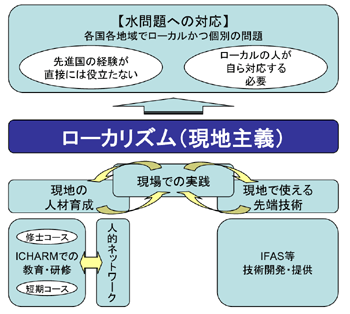
図1 ローカリズムによる対応
ICHARMでの最大のチャレンジ-それは「ローカリズム」だと竹内氏は語ります。
日本は災害多発国であり、被災経験からくる災害対策の知識による貢献を世界から期待されています。水災害対策における日本への期待-それは、衛星や観測技術、解析やITネットワーク技術など予警報にかかる先端技術です。しかし、世界では、先端技術が役に立つという段階でない地域もあります。むしろそういう地域の方が多いと言えるかもしれません。それは、社会の様相が全く異なることに起因します。
そうした地域に対して、どのように貢献するか。
特に水問題は、各国各地域でローカルかつ個別の問題です。個別の問題をどう理解し、どう解決するか。これを竹内氏は「ローカリズム」=現地主義と呼んでいます。
■■人のネットワークが支えるローカリズム
ローカリズムの実践のために自分に何ができるか-考え抜いた竹内氏がたどり着いた答えは「教育」でした。教育を軸に、ローカリズムを実践するグローバルな人的ネットワークを目指したのです。竹内氏の最初の行動は、「水災害マネジメントコース」という1年間の修士コースの設置でした。これは従来の短期コースでは難しかった「人的ネットワーク」の形成を長い目で見据えた竹内氏の行動でした。
途上国では学位取得がキャリアにつながります。その継続で水災害を担う人の体制が各国で整っていくことになるため、竹内氏は政策研究大学院大学と土木研究所のICHARM、JICAと共同で修士コース(2010年度からは博士コースも開設)を開設したのです。さらに、卒業生が現在の学生と連絡を取れるようにするとともに、短期コースを出た人たちが、帰国後に、学んだ技術やトレーニングを、周囲に教えるためのアフターケアプログラムも作成するなど、ICHARMでは人的ネットワークの維持にも配慮しています。
こうした取り組みは始まったばかりですが、すでに現地の人が主体となった人的ネットワークが張られ始めており、竹内氏が目指すローカリズムは形を整えつつあります。
■■あえて、不完全なものを
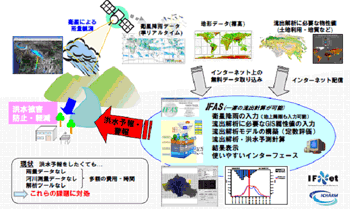
図2 IFASの機能
またローカリズムを実践するためのもう一つの行動として、ICHARMで世界中のどの流域でも洪水予測が可能となるモデルを開発しました。それがIFAS(Integrated Flood Analysis System)です。開発にあたり「地上観測降雨データのないところでも、まずは世界中のどこでも入手できるデータ、衛星観測データを用いて予測する」という点が重視されました。
予測技術はハイテクであり、これまでは先進国でしか行うことができず、しかも現地の観測データがなければ何も始められない状態でした。「データをもってくれば予測し、結果のデータを提供する」という従来のスタイルを転換し、「先進国は、トレーニングを含んだモデルを提供する」としたのが、IFASです。
IFASを使うことで、誰でも入手できるデータから、現地の技術者が必要なものを選択し、自ら予測を行えるようになったのです。
ところが竹内氏は「衛星データだけでよい予測ができるわけがない」と言いきります。
■■考え、行動するために
予測精度が粗くても、予警報が役に立たないということはありません。しかし、その段階にない地域が多いのが途上国の実情です。予警報を誰が出すのか。逃げろと言うべき人が真っ先に逃げてしまう。避難すると泥棒の被害が心配だから逃げられない等々、予警報が役に立たないのではなく、役に立てることができない状態にあるのです。
「だからこそ、現地の人が、自らその予警報技術を使うことが大事になる」と竹内氏は語ります。
現地の人が、自らの経験や地域の実態に沿って、どういう使い方をすれば予警報を役立てることができるかを考えるには、自ら予警報を出せるようにならなければ意味がない。そうすれば、実感を持って伝達の計画を立てることができ、予警報と実態が異なれば地域にあった予警報を出せるよう改善していくこともできるようになっていくと、竹内氏は考えています。
「完全なものを提供するのではなく、不完全だがそれなりに使えるものを提供し、地域のために実際に役立てるためには何を追加する必要があるかを自ら気づき、考え、作り上げることにつなげることが重要だ。」と竹内氏は続けます。
その気づきが、「自分たちがこの地域でやらなければいけない」という思いにつながり、そこから地域のオピニオンリーダーが誕生し、ローカリズムの実現につながっていくと竹内氏は考えています。
■■ICHARMが目指すもの
他から与えられたことをこなすのではなく、地域を理解し、地域に根ざした行動するエンジニアを育てるスキーム。竹内氏の思いがICHARMの活動に込められています。
地域に根ざし、地域を理解し、地域のために行動する。竹内氏は、ICHARMという場で、そういう技術者を送り出しています。
行動する技術者たち取材班
中島敬介 Keisuke NAKAJIMA 株式会社エイト日本技術開発 東京支社 都市・マネジメント部プロジェクトリーダー
参考文献
1)ICHARM HP
2)ICHARM ニュースレター第1~13号(2006/3~2009/7)
2009.11.12
| 添付 | サイズ |
|---|---|
| 322.76 KB |
