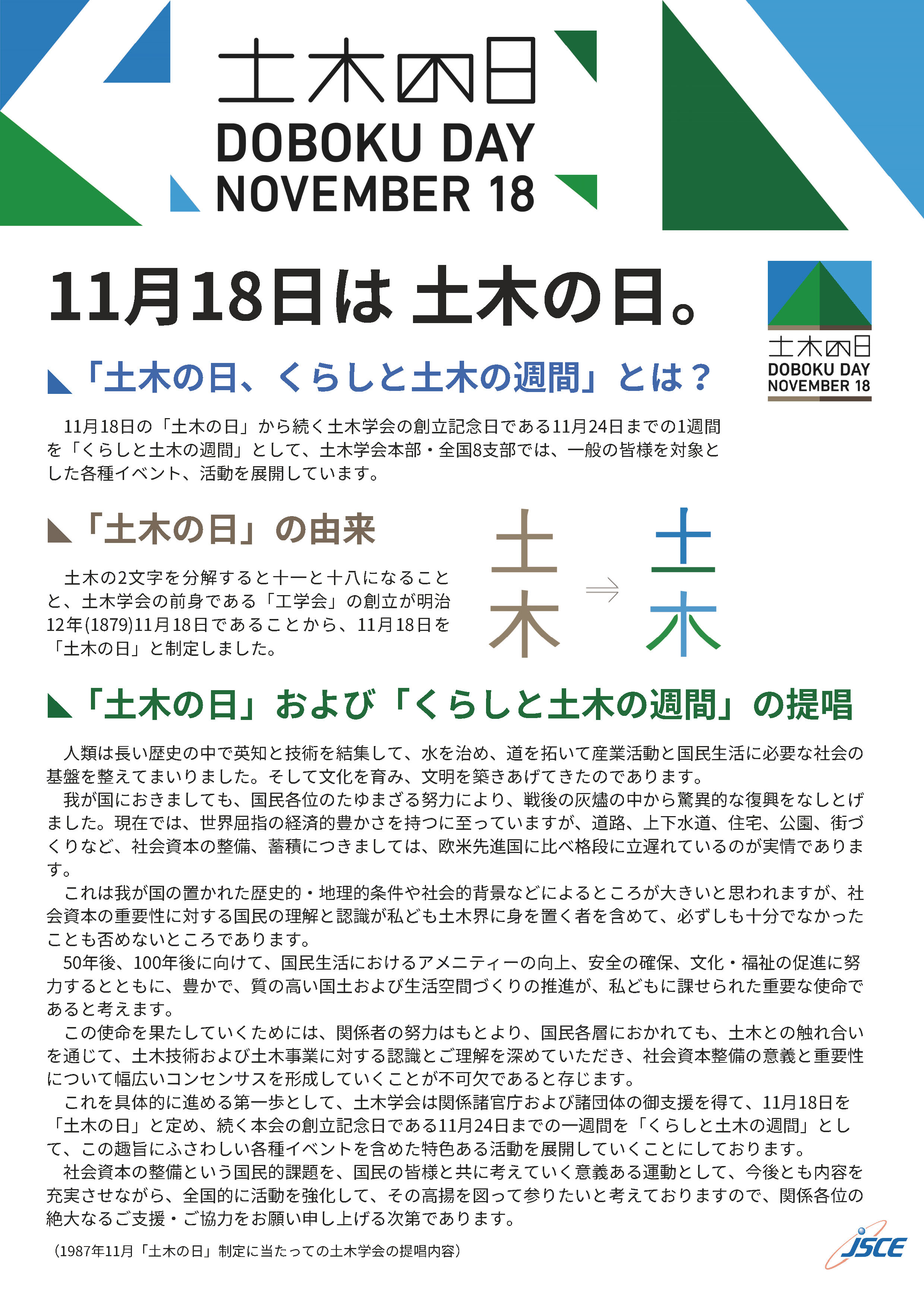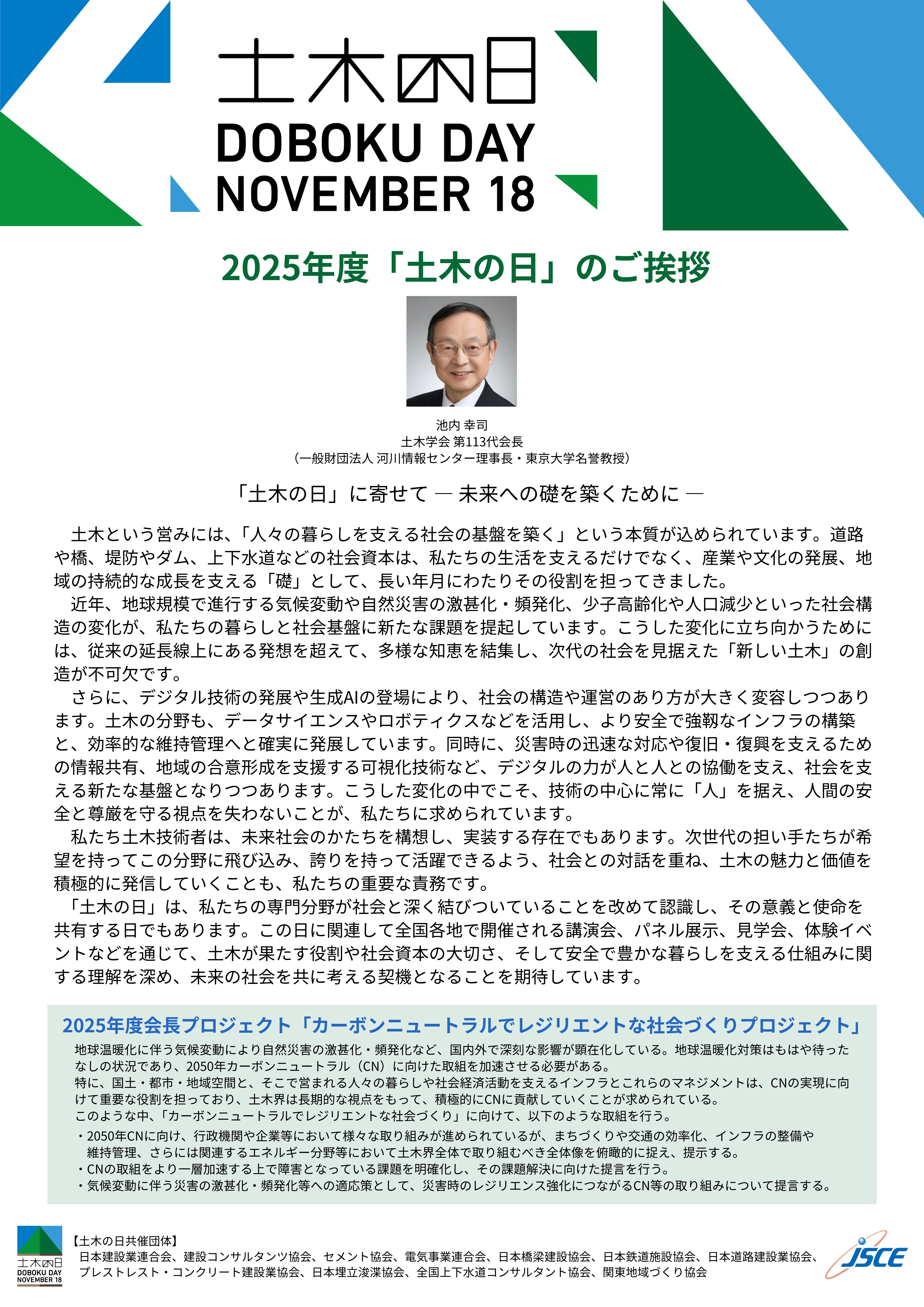|

「土木の日」に寄せて ― 未来への礎を築くために ―
土木という営みには、「人々の暮らしを支える社会の基盤を築く」という本質が込められています。道路や橋、堤防やダム、上下水道などの社会資本は、私たちの生活を支えるだけでなく、産業や文化の発展、地域の持続的な成長を支える「礎」として、長い年月にわたりその役割を担ってきました。
近年、地球規模で進行する気候変動や自然災害の激甚化・頻発化、少子高齢化や人口減少といった社会構造の変化が、私たちの暮らしと社会基盤に新たな課題を提起しています。こうした変化に立ち向かうためには、従来の延長線上にある発想を超えて、多様な知恵を結集し、次代の社会を見据えた「新しい土木」の創造が不可欠です。
さらに、デジタル技術の発展や生成AIの登場により、社会の構造や運営のあり方が大きく変容しつつあります。土木の分野も、データサイエンスやロボティクスなどを活用し、より安全で強靱なインフラの構築と、効率的な維持管理へと確実に発展しています。同時に、災害時の迅速な対応や復旧・復興を支えるための情報共有、地域の合意形成を支援する可視化技術など、デジタルの力が人と人との協働を支え、社会を支える新たな基盤となりつつあります。こうした変化の中でこそ、技術の中心に常に「人」を据え、人間の安全と尊厳を守る視点を失わないことが、私たちに求められています。
私たち土木技術者は、未来社会のかたちを構想し、実装する存在でもあります。次世代の担い手たちが希望を持ってこの分野に飛び込み、誇りを持って活躍できるよう、社会との対話を重ね、土木の魅力と価値を積極的に発信していくことも、私たちの重要な責務です。
「土木の日」は、私たちの専門分野が社会と深く結びついていることを改めて認識し、その意義と使命を共有する日でもあります。この日に関連して全国各地で開催される講演会、パネル展示、見学会、体験イベントなどを通じて、土木が果たす役割や社会資本の大切さ、そして安全で豊かな暮らしを支える仕組みに関する理解を深め、未来の社会を共に考える契機となることを期待しています。
池内 幸司
土木学会 第113代会長
(一般財団法人 河川情報センター理事長・東京大学名誉教授)
|