現在地
第6回アジア土木技術国際会議
アジア土木技術国際会議(CECAR)
第6回アジア土木技術国際会議(6th CECAR)開催報告
アジア土木学協会連合協議会(ACECC)担当委員会
委員長 山口栄輝 幹事長 鳥居雅之 幹事 中野雅章
1.はじめに
2013年8月18日~19日にアジア土木学協会連合協議会(Asian Civil Engineering Coordinating Council;略称ACECC)の第25回理事会(25th Executive Council Meeting;略称25th ECM)、8月20日~22日にACECC主催の第6回アジア土木技術国際会議(6th Civil Engineering Conference in the Asian Region;略称CECAR6)が、インドネシアのジャカルタで開催された。
ACECCは、アジア地域の土木関連学協会を束ねる連合組織として、1999年9月に発足した。多国間連携のもと、アジア地域が抱える社会資本整備や土木技術に関する課題を討議し、問題解決を図ることを主たる役割としている。土木学会は、ACECC発足当初からのメンバーであり、ACECCの活動で常に中心的な役割を果たしている。
本稿では、25th ECM、CECAR6および関連行事を報告する。
2.第25回理事会
| ECMは、ACECCの最高議決機関であり、年に1~2回の頻度で開催されている。メンバー学協会会長等の代表者が出席し、ACECCの運営方針や活動内容について協議する。25th ECMには、橋本鋼太郎土木学会会長、磯部雅彦次期会長をはじめ、土木学会からは12名が参加した。(写真1) ACECCでは、組織拡充に向けての活動も行っている。その成果として、今回、バングラディシュ工学会(The Institution of Engineers Bangladesh;略称 IEB)の加盟が承認された。これにより、11ヵ国(日本、アメリカ、フィリピン、台湾、韓国、オーストラリア、ベトナム、モンゴル、インド、インドネシア、バングラディシュ)の学協会がACECCメンバーとなった。 |
 写真1 25th ECM |
また、25th ECMにはネパール技術者協会(Nepal Engineers' Association;略称NEA)がオブザーバーとして参加しており、次回のACECC ECMで加盟が審議される。
持続可能な社会を継続するには、次世代土木技術者の育成が重要である。この点は、すべてのメンバーが認識しており、これに関する小委員会を設置し、対応を検討することが全会一致で承認された。また、ACECC憲章(Constitution)と細則(By -law)の見直しについても小委員会を設置して検討することとなった。
技術委員会(Technical Committee)の活動も報告された。日本が主査を担当して活動中の技術委員会は、鉄道技術、河川環境、ITS技術に関する3委員会である。
なお、会長挨拶等の中で、土木学会が来年創立百周年を迎え、2014年11月19日~21日に記念事業が開催されることが述べられた。特に、その一環として開催される国際シンポジウムへの参加が呼びかけられた。
3.JSCE 技術者交流プログラム
CECAR6 には、日本から産官学の多数の技術者が参加する。この機会を利用し、インドネシアのインフラ整備に関わる日本人技術者との交流会が、CECAR6 開催前日(8月19日)に開催された。前半は技術者交流会として、海外へのインフラ展開やインドネシアにおけるインフラ整備の現状について、国土交通省、JICA、日本工営ならびに大林組から計4件の話題提供があり、その後、我が国の建設産業の国際化に向けた方向性や、土木学会としての国際活動の在り方について、熱心な意見交換が行われた。後半は、参加者による懇談会を開催し、またインドネシア在住の元留学生を招待し、交流を持った。
4.第6回アジア土木技術国際会議
CECARは、各学協会会長をはじめ、産官学の主要メンバーが一堂に会する国際会議で、3年ごとに開催される、ACECCの一大イベントである。第1回CECAR は1998年にマニラで開催され、ACECC設立のきっかけとなった。2001年には、土木学会が運営を担当し、東京で第2回CECARが開催された。
CECAR6は、インドネシアからのACECCメンバーであるインドネシア土木構造工学会(The Indonesian Society of Civil and Structural Engineers;略称HAKI)が運営を担当し、Embracing the Future through Sustainabilityをテーマに開催された。
(1)開会式
会議の初日、CECAR6運営委員長Imran氏、ACECC会長Hoedajanto氏、インドネシア公共事業省大臣Kirmsnto氏(副大臣が代理出席)のスピーチからなる開会式があり、CECAR6が開幕した。(写真2)
引き続き、ジャカルタ協定(Jakarta Protocol)の調印式が行われた。本協定はCivil Engineering for a Sustainable Futureと題するもので、持続可能な未来に向けて、ACECCメンバーの学協会が責任を負っていくことを誓うものである。調印式には、橋本鋼太郎土木学会会長をはじめ、メンバー学協会の会長が一堂に会し、協定書に署名した。(写真3)
 写真2 CECAR6開会式 |
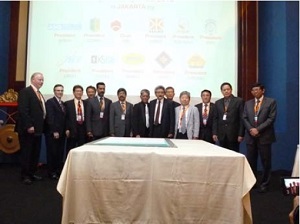 写真3 ジャカルタ協定調印式 |
(2)研究発表
|
CECARでの発表は、基調講演、一般講演セッション、オーガナイズドセッションに大別される。 |
 写真4 藤野東大教授による基調講演 |
オーガナイズドセッションは、ACECCのメンバー学協会や技術委員会が企画し、運営するものである。土木学会は、Asian Board Meeting、 Tsunamiセッション、ITSセッションの企画・運営に中心的な役割を果たした。
Asian Board Meetingは、昨年度の全国大会でRound Table Meeting として実施されており、CECAR6での開催が2回目となる。自然災害をテーマに、アジアを中心とした国々の行政や学協会からの発表、意見交換をもとに、防災/減災に向けての協力体制構築を目指すものである。今回はLessons learned from Past Natural Disastersをテーマに開催された。橋本土木学会会長の開会挨拶、磯部土木学会次期会長の主旨説明に続き、国土交通省、アメリカ土木学会、インドネシア公共事業省、ミャンマー運輸省、ネパール技術者協会、フィリピン土木学会、中国土木水利工程学会(台湾)から発表があった。これらの発表をもとに、上田多門土木学会国際センター長を座長として、聴衆も交えて議論が行われた。非常に多くの意見が出され、予定時間を大幅に超過してようやく終了した。最後に、2014年11月の土木学会創立百周年行事の一環として、第3回Asian Board Meetingが開催予定であることがアナウンスされた。
Tsunamiセッションは、佐藤慎司氏(東京大学)の尽力により、土木学会、インドネシア土木構造工学会、フィリピン土木学会の共催で行われた。日本が主催しているACECC技術委員会のひとつがITS-based Solutions for Urban Traffic Problems in Asia Pacific Countries (TC16) であり、委員長を務める牧野浩志氏(中日本高速道路)が中心となって、ITSセッションが開催された。
ACECC自体も、Presidential Session in Infrastructureと題するオーガナイズドセッションを企画した。これはACECCメンバー学協会の会長が、所属機関を代表して発表するセッションであり、7件の発表があった。土木学会からは橋本会長が登壇し、Infrastructure Maintenance and Renewal for Achieving Sustainable Societyと題する発表を行った。
(3)ACECC賞
ACECCでは、プロジェクト賞(ACECC Civil Engineering Project Award)と業績賞(ACECC Civil Engineering Achievement Award)を設け、CECARで表彰している。
プロジェクト賞は、直近の概ね3年間に、土木技術の進歩とアジアの発展に顕著な貢献のあったプロジェクトに授与される。その中でも、特に優れたプロジェクトは、ACECC Outstanding Civil Engineering Project Awardとして賞される。今回は、中日本高速道路株式会社の「新東名高速道路の建設(Construction of a world-leading、 next-generation expressway "The Shin-Tomei Expressway")が、Outstanding Civil Engineering Project Awardの栄誉に浴した。
業績賞は、国際的な土木技術の進歩や、アジアまたはACECC参加国の社会資本の発展に顕著な貢献があり、その業績が国内において認められているACECC参加国に属する個人に授与される。土木学会が推薦した岡田宏氏(元土木学会長、日本交通協会)をはじめ、3名が受賞した。(写真5)
5.海外学協会との協力協定
ECM、CECARには、土木関連学協会の会長が集う。この貴重な機会を利用して、今回、土木学会とHAKIとの間で、新たに協力協定が締結された(写真6)。また、土木学会とNEAとの協力協定が更新された。
 写真5 ACECC受賞者(左端:岡田宏氏、右から2番目:中日本高速(大川氏)) |
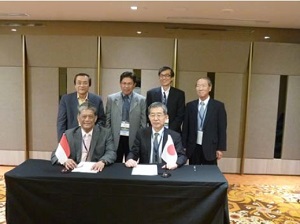 写真6 土木学会とHAKIの協力協定締結 |
6.JSCE主催:「バリ島緊急海岸保全プロジェクト」視察ツアー
| CECAR6後の8月23日には、前回ACECCプロジェクト賞を受賞した標記の視察ツアーを実施した。本プロジェクトはバリ島のリゾート海岸における海岸侵食、サンゴ環境の悪化問題等について、その海岸環境の復元を目的とする日本のODA(円借款事業)として、1987年のF/S調査から2008年までの工事完了まで、長期間にわたって実施されたものである。 今回の視察ツアーでは、本プロジェクトの計画段階から長年関わってきた日本工営(株)の大中晋氏の案内により、プロジェクトが実施された3海岸(クタ、タナロットおよびサヌール)を視察し、当時の技術的な課題と解決策等に関わる具体的な取り組みを知ることとなった。またプロジェクト完了から10年以上経過した現在の海岸状況や、多くの観光客が訪れる様子を観察することにより、日本のソフト・ハード両面における高度な技術とその技術のアジアへの貢献を実感することができた。(写真7) |
 写真7 バリ島緊急海岸保全プロジェクト |
7.おわりに
次回の7th CECARは、2016年にハワイで開催される。アメリカ土木学会(The American Society of Civil Engineersn;略称ASCE)が運営を担当する。 CECAR6の最終日、閉会式において、HAKIからASCEへの引き継ぎが完了した。この日をもって、ACECC会長にはASCEのAlbert Yeung氏(香港大学)、ACECC事務局長には土木学会の堀越研一氏(大成建設)が就任し、新たな体制が発足した。
これまでACECCの運営は、CECARを担当する学協会が中心になって行ってきた。ACECC会長のみならず、ACECC事務局長もその機関から選出された。このような方法では、3年ごとにACECC幹部全員が交代することになり、首尾一貫したACECCの運営は容易でない。その反省から、ACECC事務局長は、CECAR担当学協会と無関係に選出することになった。
このような経緯のもと、2012年9月にマニラで開催されたECMにおいて、堀越氏が次期事務局長に選出され、今般、ACECC事務局長に就任した次第である。ACECCにおける土木学会の役割がさらに大きくなった。
●ダウンロード用PDFはコチラ
