現在地
第108回土木学会イブニングシアター(2020.1.22)
あの素晴らしい土木技術をもう一度
第108回土木学会イブニングシアター
~トンネル特集~
多数のご来場、誠にありがとうございました。
|
今回のイブニングシアターでは、「トンネル」をテーマに2作品上映します。
18:30 開会挨拶
|
|
上映作品
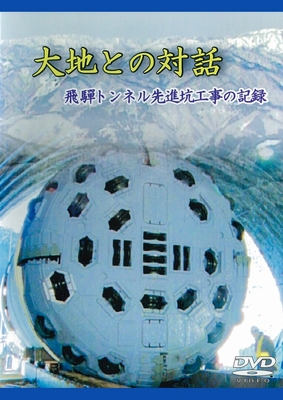 |
大地との対話-飛騨トンネル先進坑工事の記録- |
|
東海北陸自動車道の最後の未開通区間である飛騨清見IC~白川郷ICに大きい障壁となっている籾糠(もみぬか)山を貫く飛騨トンネルの先進坑工事の記録である。高圧湧水帯におけるTBMの立ち往生,切羽の崩壊等,通常の工事記録映画ではあまり見られない生々しい工事現場の苦闘を表現しており,貴重な映像といえる。 |
|
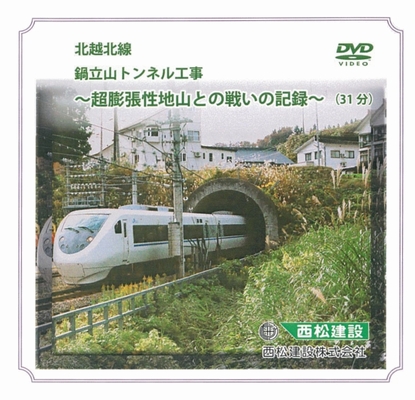 |
北越北線 鍋立山トンネル工事~超膨張性地山との戦いの記録~ |
|
この映画は超膨張性地山のトンネル工事現場における撮影映像をベースに作られた記録作品である。立ちはだかった地山の押し出してくる膨張圧力は実に30kg/cm2,地山に内在した可燃性ガスの圧力は実に16kg/cm2に達した。おそらく日本で最も過酷な膨張性地山でのトンネル施工例と考えられる。 別の見方をすれば,これは「結果論として掘ってはいけなかったトンネル例」の紹介であり,「引いてはいけないトンネルのルート選定例」でもあり,トンネルルートの選定に際しての調査の重要性を鋭く示唆している作品である。しかし,9,116mに及ぶ本トンネル延長のほぼ真ん中で最後にこの600mほどの地層が出たとき,技術者達は全知全霊を掛けて果敢にこのトンネルを掘り抜くしか選択の道はなかった。作品はそれを成し遂げた男達の苦闘の記録でもある。 映像は技術者達の想像を絶する過酷な超膨張性地山との戦いとこの過酷な工事状況を,現場の貴重な実写フィルムと分かりやすいアニメーションとで表現しておりトンネル歴史資料としても1級の技術映像資料と考えられる。折しも本年作家峯崎 淳氏による『「動く大地」の鉄道トンネルー世紀の難関「丹那」「鍋立山」を掘り抜いた魂―』が発行され,このトンネル施工が持つ技術的困難性と,重要性が再評価されることになったこともあり,良いタイミングでの土木技術映像選定作品となった。 一般の方には希有で過酷な自然に立ち向かったトンネルマン達の不屈の挑戦記録として,専門の方には高圧ガスを伴った最大級の超膨張性トンネルの実工事施工記録として,是非この貴重な工事記録を多くの人に見て頂きたいと思う。 |
|
以上

