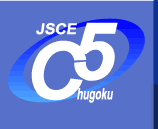現在地
歴代支部長挨拶
 |
平成24年度 土木学会 中国支部長
|
|
平成24年度の土木学会中国支部長を仰せつかりました末國光彦と申します。どうぞ宜しくお願いいたします。 はじめに,平成23年度の事務局の任にあたられました井上正一支部長,西村強幹事長,黒田保事務幹事におかれましては,支部活動の活性化,公益社団法人移行の初年度対応,中国支部70周年記念事業の開催など,支部の事業運営にリーダーシップをいかんなく発揮されご尽力をいただきましたことに,心より御礼申し上げます。 さて,平成23年に発生した地震,津波,水害などの多くの自然災害を目の当りにした私たちは自然の猛威に完膚なきまでに叩きのめされ感がありますが,人々はそこから立ち上がる精神まで萎えてはおらず,その底力が困難な復旧・復興への道の原動力となっており,また着実な歩みを続けておられる姿は強い絆を持って応えなければならないというボランタリーな心を多く芽生えさせたのも事実ではないでしょうか。 しかしながら,ネガティブな要素の多い社会環境では,人々の体感的な不安・不信が頭をもたげ,大衆迎合的,興味本位,事実に基づかないバイアスのかかった情報が独り歩きしている状況が散見されるのも事実です。このような社会環境だからこそ,「今一度原点に帰る」「足下を見つめ直す」「事実に基づく基軸を持つ」ことが大切なのではないでしょうか。 土木学会の古市公威初代会長は就任演説の中で,「土木技術者は『指揮者を指揮する人』『将に将たる人』たらねばならぬ」ことを力強く述べられ,土木学会会員に「研究の範囲を縦横に拡張せられんこと」「その中心に土木あることを忘れられざらんこと」を訴えられています。この精神は,社会環境の急激な変化や巨大災害リスクに敏感に対処しなければならない現在においても欠くべからざるもので,本学会・学会会員は「市民工学(Civil Engineering)」に関わる者として,公益増進への不断の努力を継続し,次世代に向け新たな一歩を歩みださなければなりません。 激変する社会環境の中で,支部活動においては,地域における活動資源のうち最も重要な「人(ネットワーク)」に係る事項に力点を置き, 遅々として進まない震災復興やエネルギー政策論議,グローバリゼーションの進展,少子高齢化の加速,地球環境問題への対応や巨大災害リスクへの備えなどの課題に加え,国家財政や経済の先行き不透明感などの課題が示すように,極めて厳しい社会環境に劇的に変化した時期に,大役である支部長に就任しましたからには,公益性の高い電気事業に身を置く技術者の一人ではありますが,微力ながら「鞠躬尽力」の心で取り組む所存です。 支部会員の皆様の一層のご協力とご指導をお願い申し上げ,支部長就任の挨拶といたします。
|
|
平成23年度 土木学会 中国支部長
(鳥取大学大学院工学研究科教授) |
|
| 平成23年度の土木学会中国支部長を仰せつかりました井上正一と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
初めに,三浦房紀前支部長,麻生稔幹事長,吉武勇事務幹事におかれましては,支部活動の活性化,公益法人対応,中国支部の緊急災害調査委員会の組織化と初めての出動,さらには本年度開催の「中国支部70周年記念事業」の計画・推進に向けて優れたリーダシップを発揮され,土木学会中国支部をお導き頂きましたことに,心より御礼を申し上げます。有り難うございました。 さて,土木学会とその会員の営為は,ハード・あるいはソフト面からの社会基盤の整備を通して,国民の生命と生活,財産を守り,安全・安心を確保することにあり,私達はそのような貢献をしているという自負や誇りを持っておりますが,昨今は,そのことが評価されず,「コンクリートから人へ」などと揶揄され,市場も縮小の一途で,この先も不透明な状況になっておりました。 そんな中,北陸を中心に史上最悪の豪雪被害に見舞われ,宮崎・鹿児島県境の新燃岳が200年ぶりに噴火という異常気象,異常事態に続き,本年3月11日には,地震に加え,津波,原発の放射能漏れによる未曾有の被災を被り,都市機能も田畑もライフラインもガタガタ。日本における社会基盤の貧弱さと,政治・社会・経済・外交等々,我が国の危機管理について,国の仕組みまでリセットして本気で考えないと,このままメルトダウン,下り坂を転がり落ちていくような気がしてなりません。 今回の震災,復興・復旧にはこれから何年もかかると思います。①土木とは何か,②土木技術者として今何をなすべきか,そして将来はどのような方向を目指すべきか。この重い命題に対して国レベル,さらには中国地方において災害時の緊急行動や常態時の行動を通して,真に人々の生命・生活の安全・安心を確保し,かつ国と国民を豊にするためには何をなすべきかについて学会員や国・県の皆さん,一般市民の皆様と一緒に模索・検討していきたいと考えています。 それから,常態時の支部活動として,③技術の伝承を重視し,これを実現する環境整備を構築していきたい。具体的には,まず,土木技術者が地道に果たしてきたこれまでの行動や実績を正確に広報するとともに,社会基盤整備は恒久的に必要不可欠であることを若い世代に啓蒙し,土木の魅力を知ってもらう。一方で,意識の高い学生を集めて教育し,夢・希望に満ちた学生を魅力ある健全な業界に送るというシステムを再構築する,いわゆる正のスパイラルを構築する。そのために,若い会員の増員に注力したい。社会基盤整備の重要性に関しては,今,何故,社会基盤整備が必要か?予防は治療に勝ることを訴え,社会基盤を維持・管理していくために必要な適正な予算確保に努める一助になるよう貢献していきたいと考えております。会員サービスに関しては,できる限り地元の会員が講師を担当し,地元の技術を紹介する,あるいは地元が抱える問題について技術者と一体となったきめ細かな講習会も企画していきたいと考えています。 日本復興,エネルギー政策論議,土木学会の公益法人化と会員数の減少,国際競争力の維持・強化,グローバル化など,激動の変革期に,大役である支部長に就任しましたからには,微力ではございますが全力を尽くす所存です。 支部会員の皆様の一層のご協力とご指導をお願い申し上げ,支部長就任挨拶といたします。 |
|

平成22年度 土木学会 中国支部長
三浦 房紀 (山口大学大学院理工学研究科教授)
“コンクリート”こそが人の命を守る ~東日本大震災について~支部長からのメッセージ
平成22年度土木学会中国支部長を仰せつかりました、山口大学大学院理工学研究科の三浦房紀と申します。この一年間会員の皆様、また関係者の皆様には様々な面でお世話になると思います。どうぞよろしくお願いいたします。
さて、昨年夏、政権が交代し、「コンクリートから人へ」というキャッチフレーズが一世を風靡しました。“コンクリート”とは公共工事等の総称と考えられますが、そこからは、まるで公共工事は悪であるような、あるいはもう必要のないものであるようなニュアンスが伝わってきます。また実際そのような報道もあったかと記憶しています。しかしながらこれはとんでもない勘違い、あるいは国の進むべき方向を誤らせる危険性を孕んでいると私は思っています。
私の専門は地震工学、防災工学ですが、災害という面から過去を振り返ってみますと、昨年は昭和34年(1959)の伊勢湾台風からちょうど50周年に当たる年でした。この伊勢湾台風では高潮により約5000人の犠牲者が出ており、この年だけで風水害で約6000人もの人が命を失っています。じつはそれまでも毎年のように数千人が風水害で犠牲となっていたのです。この伊勢湾台風が契機となって災害対策基本法が制定され、国、都道府県、市町村が力を結集してダムの建設、河川堤防の整備、海岸の整備、道路の整備、すなわち公共事業を進め、急激に風水害による犠牲者を減少させることに成功しました。すなわち、“コンクリート”こそが命を守った、といっても過言ではありません。
地震による災害はと言えば、約3800人の犠牲者を出した昭和23年(1948)の福井地震以後、平成7年(1995)阪神・淡路大震災まで、犠牲者が1000人を超す地震は全く起こりませんでした。しかしながら福井地震以前は、明治以降1000人を超える犠牲者の出た地震が10回も起こっています。これは日本、特に西日本が地震の活動期だったからです。
福井地震から阪神・淡路大震災の間は地震の静穏期で、これと上述の公共事業による風水害の激減、さらには我が国の高度成長期がこれらに重なるという、実に幸運を日本人は享受してきました。そしてその間、災害のことはすっかり忘れてしまった感があります。
阪神・淡路大震災以後、西日本は再び地震の活動期に入り、東海、東南海、南海地震は確実に近づいています。国(中央防災会議)の想定によりますと、犠牲者は条件によってはこれら3つの巨大地震によって27000人を超え、約90兆円もの被害がでる可能性があります。
その一方で、最近の雨の降り方は尋常ではありません。毎年多くの地域で降雨記録が更新されています。「数百年に一度の降雨」と聞いてもあまり驚かなくなりました。台風の巨大化による被害も大きくなっています。もはやこれまで整備してきたインフラで耐えられるかどうか分かりません。
この様なことを考えると、インフラを再度整備して国土の耐力を強くしておくことは喫緊の課題です。“コンクリート”こそが人の命を守るのです。この意味から、土木工学は極めて重要かつ不可欠な学問、技術分野です。このことを声を大にして社会に対して発言していく必要があります。そして土木工学の真の姿を理解してもらう必要があります。さもなくば、多くの人々の命を守ることが出来なくなってしまいます。
この一年間、可能な限り、社会に対して、特に報道機関に対して以上のことを皆さんと共に伝えていきたいと思っています。どうぞ宜しくお願いいたします。