現在地
【インタビュー記事】シニアに学ぶ『退職後の輝き方』
投稿者:匿名ユーザ 投稿日時:月, 2015-08-03 00:12
 noteページはこちら →https://note.com/civil_id/
noteページはこちら →https://note.com/civil_id/

私達の周りを見ると、生き生きと活動し、輝いているシニアのシビルエンジニアの方が大勢いらっしゃいます。そこで、本小委員会では、退職後も生き生きと活動しているシニアのシビルエンジニアの方に、これまでの生い立ち、各年代においての考え方や行動の変化などをお伺いし、それらをまとめたインタビュー記事を公開していくことを企画しました。 インタビューの対象者には、身近な先輩を選んでいます。また、退職後に輝くためには、現役時代からノウハウやスキルを身に付ける必要があるという観点から、読者層として40歳代、50歳代を想定しています。本企画を通して、シニアから学び、皆さまが退職後も生き生きと活動し、充実した生活を送ると共に、土木界がさらに活性化していくことを望んでいます。
「タイトル」または「委員会からのメッセージ」のクリックで記事のpdfファイルが開けます。
インタビュー記事一覧![]()
 |
|
|
第22回 末岡 徹氏 『自分に素直に生きる』 (2017/5/23更新) |
|
 |
|
|
(2017/1/23更新) |
|
 |
|
|
(2016/8/9更新) |
|
 |
|
|
第19回 山中 鷹志氏 『橋を知り、橋とともに生きる』 (2016/9/26更新) |
|
|
|
|
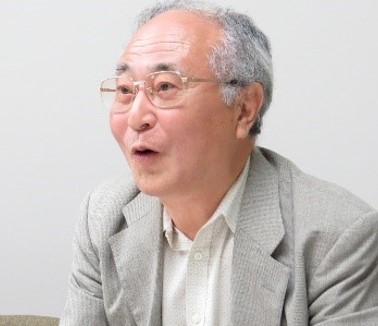 |
|
|
『自分自身で考え、挑戦し続けることの大切さ』(2016/2/7更新)
|
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
|
特別編 6つの「わざ」と五角形のコマ (2015/8/2更新) |
|
|
|
|
|
(2015/1/1更新)
|
|
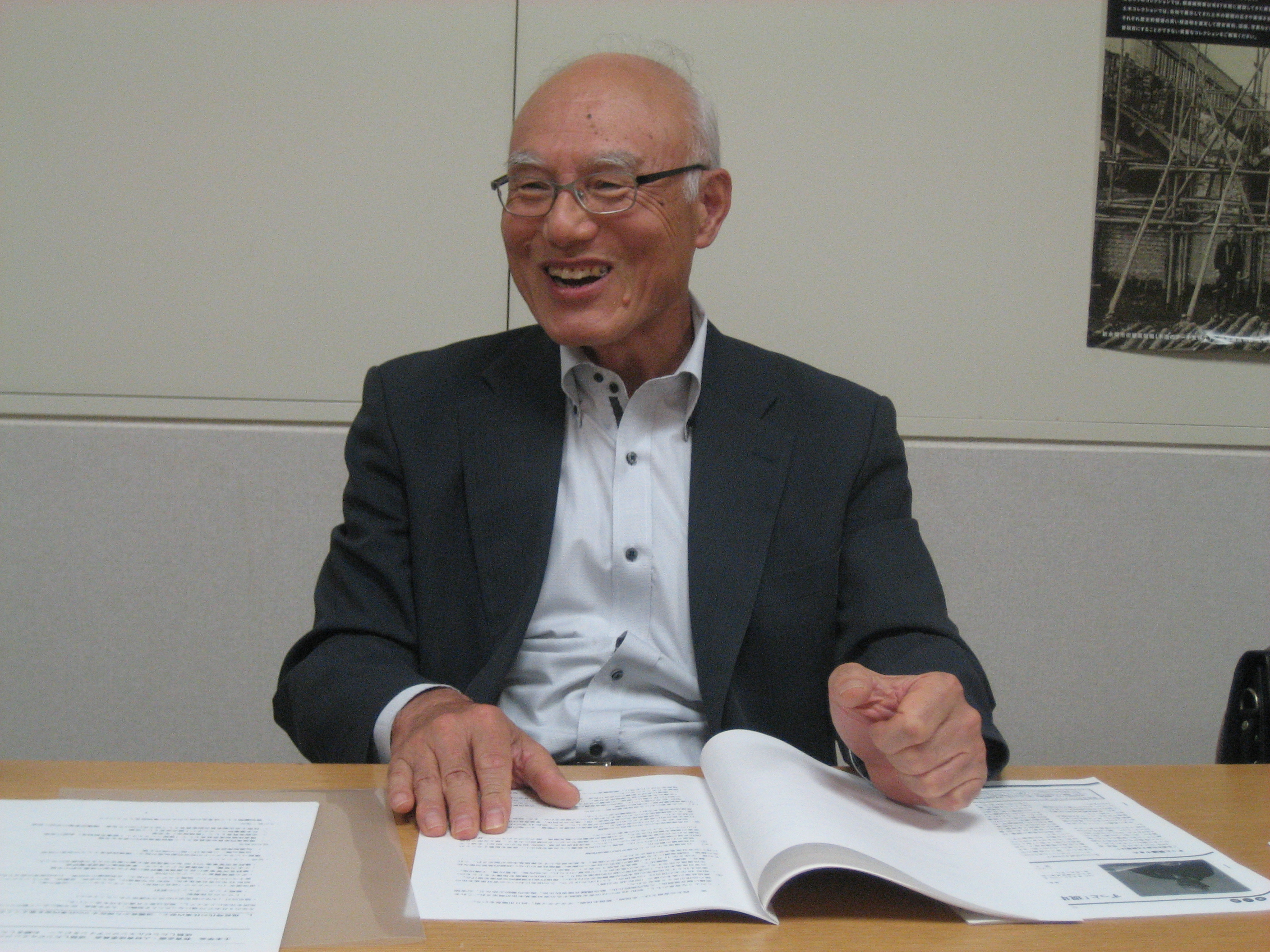 |
|
|
|
|
 |
|
第1回~第10回のインタビューの総括をしました。 |
|
 |
第 10 回“ シニアに学ぶ 『退職後の輝き 方』”では、福島県広野町で任期付職員として 活躍されている尾田栄章さんにお話を伺いまし た。尾田さんが70歳を過ぎてから取り組み始め た広野町の復興。尾田さんは着任後、広野町 を自らの足で歩いて回り、また町民を一人一人 訪問されました。 我々聞き手 3 人は、復興状況と問題点を少 しでも共有するため、広野町、そして楢葉町・ 富岡町と車で回りました。 |
|
|
|
 |
|
|
(2015/1/12更新)
|
|
 |
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
 |
委員会からのメッセージ
|
|
第5回 佐伯 光昭氏
|
|
 |
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
 |
|
 |
|


