■最優秀賞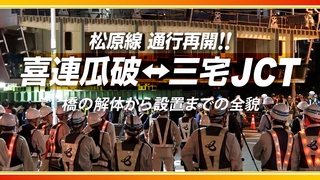
【喜連瓜破 橋梁架け替え工事】二年半の軌跡 ~100年先を見据えて~ 工事担当者の想いに迫る!
企画:阪神高速道路(株)管理本部
制作:阪神高速道路(株)
監督:阪神高速道路(株)管理本部 大阪保全部 保全管理課
2025年
作品概要
阪神高速では、2022年6月より14号松原線(喜連瓜破~三宅JCT)を終日通行止めの上、橋梁架替工事を実施した。
都市高速を長期間に渡って通行止めにするという前代未聞の工事の上、工事区間の直下には大阪市内でも有数の重交通を担う交差点があり、かつ周辺地域は密集市街地となっている。
制約条件の多い中、既設コンクリート橋桁の撤去及び鋼製橋桁の架設までを無事完了させ、2024年12月7日に約2年半ぶりに通行を再開した。
本動画は、工事着手前から通行再開までの事業の記録映像である。
■部門賞(一般部門)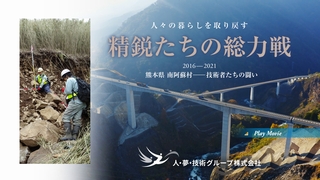
人々の暮らしを取り戻す 精鋭たちの総力戦 2016-2021 熊本県南阿蘇村―技術者たちの闘い
企画:人・夢・技術グループ株式会社
制作:葛谷正美・葛谷真由美
監督:葛谷正美・葛谷真由美
2025年
作品概要
平成28年(2016年)に発生した熊本地震。最大震度7を記録し甚大な被害をもたらした。
本作品は阿蘇大橋付近で発生した大規模な斜面崩落からの復旧や復興のシンボルでもある「新阿蘇大橋」開通に向けて立ち向かう土木技術者達の記録である。
震災直後から現地に入り、余震の不安の中で応急調査。その後、限られた時間の中で、技術を結集し地盤調査設計、橋梁設計を完了させる。その力の根源は、“人々の暮らしを守る”という技術者の「使命感」であった。
国民の暮らしを守るという使命感を持った技術者達の挑戦を描いている。
■部門賞(技術映像部門)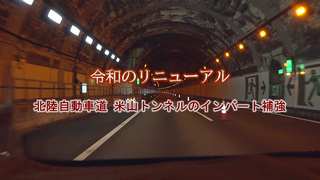
令和のリニューアル 北陸自動車道 米山トンネルのインバート補強
企画:東日本高速道路株式会社 新潟支社長岡管理事務所
制作:有限会社創映舎
監督:有限会社創映舎
2022年
作品概要
北陸自動車道の米山トンネル下り線は建設以来、盤ぶくれによる路盤の変状が進行していた。本作品は、令和3~4年度に行ったインバート補強による補強対策工事の記録を映像としてまとめたものである。